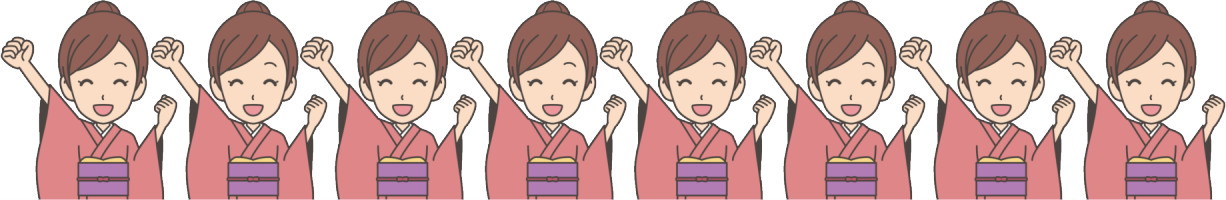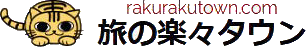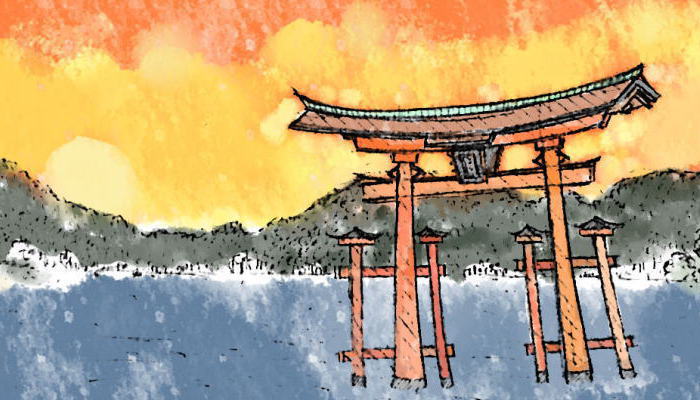温泉旅館物語
昭和43年(1968年)、26歳になった「湯の街ネヲン(以下、ネヲン)」は、伊豆熱川の温泉旅館に就職した。これは、運命の神様のお導きで、自分の意志では絶対に選択しなかった職業で、その後、生涯にわたってお世話になった。時代は高度成長期、温泉旅館業界も好景気の波が押し寄せ始めていた。当時の伊豆は新婚旅行ブームで、半島巡りの定期観光バスには、日に、1,000組もの新婚さんが乗っていた。バスガイドさんの話によると、「車中での新婚さんたちは皆さんぐっすりと眠っていた」そうだ。
この時代の旅なれたお客さんたちは、おおらかであり、温泉旅行デビューする庶民たちは、旅先で恥をかかないようにと勉強し、お行儀よく振舞っていた。お膳に並ぶ料理は、地元の新鮮の食材を、板前さんが手間ひまをかけ、見た目にも芸術品のようであった。掃除は行き届き、シーツや浴衣は天日干しでバリバリ、お日様の匂いがして気持ちがよく、お土産物は地域の特産品であった。泊る人と泊める人の間には素晴らしい関係があった。
ネヲン、旅館勤めを始めてすぐに感じたことがあった。それは、すべてのお客さんが「また来るよ」と言って、ニコニコ顔で帰っていくことである。旅館って「魔法の館か?」と思った。「なんでだ?」と不思議に思ったネヲン、あたりを見回した。まず、目についたことが、館内には、すべての職種で二十歳前後の従業員であふれかえっていた。ほとんどが地元・伊豆の出であった。特に、若い女中さんたちは、みんな素直で従順だった。
普段は、「~だら」と、伊豆弁丸出して元気で活発な女中さんたちが、お客さんとの会話のときは、たどたどしい標準語となった。そんな会話が聞こえた時は、思わず吹き出しそうになった。どの娘たとも、精一杯のおもてなしをしていた。お客さんたちがおおらかな気分になれたのは、女中さんたちに尊敬の念があったからである。お客さんたちは、「伊豆の踊子」の主人公、学生さんのような気分になっていた。
食べるものにも事欠いた終戦直後に生まれ育った子供たちは、親や世間の庇護のもとに従順に育ってきた。さらに、貧富の差というものを、身をもって知っていたので、女中さんたちは、お客さんを別世界の人たちとして尊敬することが出来た。もちろんお客さんも、そんな女中さんたちを暖かい目で見守っていた。蛇足ながら「女中さんの○○ちゃんを、我が家の息子の嫁に」という話が沢山あった。