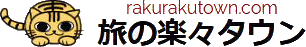序章
1968年(昭和43年)晩春、26才のオレこと「湯の街ネヲン(以下、ネヲン)」は、2年余勤務した横須賀の陸上自衛隊の除隊を決意をし転職活動を始めた。すると、これまで全く無縁であった人たちの「一言二言(ひとことふたこと)」で、あみだくじの階段を下るようにして次の職場がひとりでに決まった。
それは、職探しに行った伊豆下田の職安の不愛想なおじさんの「この旅館に行け」のひとことと、そして、横須賀のどぶ板通りで、「生い立ちのこと」を言い当てた占い師のおばさんが、「水商売に適性がある」と、言ったふたことである。
そんなわけでネヲンは、伊豆熱川温泉の「ホテル アタガワ」に就職した。この旅館は、総客室は45室で最大収容人員は250名の中規模旅館で、海一望が謳い文句であったが、すべての客室から海がバッチリではなかった。露天風呂はなく、大浴場はそこそこの大きさであったが眺望はない。なので一流旅館とはいいがたかった。

この時代は、温泉旅館業界というか「旅館の経営者」だけが黄金時代であった。それは、財力のある地元の有力者が無借金で旅館を建て、かつ、ただ同然の給料で板前、番頭、女中さんたちが雇用でき、文字通りフルに働かせることができたからだ。
社員たちはよく働いた。すべての女中さんは二十歳そこそこ。フロントには若い男が 7人もいて、フロント兼務ですべての業務をこなした。板場の人たちも若かった。
創業時以来の古参の人は、短躯で角突きの牛のような板長 兼 総支配人と、物静かな総務 兼 外回りの番頭さんと、気位の高い金庫番のおばさんだけであった。
外回りの番頭さんとは、歓迎旗をもって駅でお客さんを迎えるのが主な仕事だが、当日のフリー客を街なかで捕まえて、歩合制で自館へ連れてくることもしていた。
当時の旅館の経営者といえば雲の上の人で、旦那さんとかお父さんとか呼ばれ、仕事もせずに毎日ブラブラと競輪・競馬に麻雀、芸者遊びにと好き勝手をしていた。それでも、人手が十分にあった時代なので館内は板長を中心に滞りなくまわっていた。
こんな時代、ホテル アタガワの社長は例外中の例外であった。ひょろりとした長身で顔の長いこの40代半ばの社長は、現場での細かなことには口を出さなかったが、経営には全力をそそいでいた。ネヲン、もし、ここの社長が遊び人であったら、今頃は、場末のドブのよどみに沈んでいただろう。
社長の思いもよらない話
この物語は、ネヲンが入社以来、3年が過ぎた春の夜の社長の話しからはじまります。会話の場は、ホテル アタガワの本館「旅館 青雲閣」があった街なかで、今は立て替えをして、5階建ての社員寮 兼 社長の自宅になっている社長の書斎である。
旅館 青雲閣は、戦争中に東京から疎開した先代(以下、おばあちゃん)が、1950年(昭和25年)に熱川の街なかで創業し、当時はこの熱川で三番目の規模を誇った温泉旅館であった。
ある夜、ネヲンは社長宅の書斎に呼ばれた。書斎には、木製の立派な机が一つでんと置かれていた。そこは、メインストリートぞいにあり、向かいの遊技場のネオンの瞬きがくもりガラスの窓に映ったり、酔客の嬌声や下駄の音などが響いてきた。
社長に呼び出されたといっても一大事ではない。社員教育に熱心な社長は、時や場所を選ばず、社員をつかまえては、館内での出来事や世間話をうまく取り入れて、相手のレベルに合わせて解りやすく話して聞かせていたからごく普通のことだった。

焼酎が二杯
糖尿病がある社長は夕食後の酒の量に制限があり、焼酎がきっちり二杯と決まっていた。ネヲンが入室すると、まだ春だというのにランニングシャツとステテコ姿で、長い脚を組み、すでに顔を赤らめ一すじ二すじと汗を流しながら待っていた。特に太っているわけでもないのに、とても汗かきであった。
この夜の話は、ネヲンとって思いもよらないものであった。社長は、長い人差し指で足元の絨毯を差しその指先を上下に動かしながら、「ところでネヲンさんは、ここに来てどのくらい?」と、訊いた。
この社長は、どの社員にも必ず「さん」づけで呼ぶ。そして、下の社員になればなるほど優しい笑顔と声音で話しかける。
「3年です」と、ネヲンはいつものようにぶっきらぼうに答えた。
「そうか、もう3年も経ったのか!」と、社長は感慨深げにいって、
「毎日毎日、同じ仕事ばかりでは飽きるだろう」と、続けた。
「どう云うことですか?」とネヲン、経理だもの仕事が繰り返しなのは当たり前だろうと思いながら、社長の真意がわからず聞き返した。
「たまには都会の空気でも吸って気分転換をして来い、セールスということで外に出すから」と、社長は解説をした。
「セールスですか!?」とネヲン、セールスなんて夢にも思ったことがないので驚きの声を発した。陸上の選手が、いきなりプールに飛び込めといわれたようなものだ。
「バカ! お前に客が取れるなんて、これっぽっちも思っちゃいない」と社長、
「第一、お前はぶっきらぼうのうえに、顔からしてセールス向きでない」と、ひどい言いようをした。
でもネヲンは、この言葉に自分自身が妙に納得してウン、ウンとうなずいた。すると、社長はさらに、信じられないことを言った。
「ネヲンさんや」と、社長はおだやかにいってひと呼吸おき、長い指を一本づつ折おりまげながら、月、火、水、木、金、と言い、今度はその折り曲げた指をパッとひろげて、ネヲンの顔の前でヒラヒラとさせながら続けた。
「気分転換のためにセールスという名目で出張させるのだから、5日のうち3日間は映画を見るなり好きにしていい。ただ、ほかの社員の手前があるから、2日間は営業のまねごとをして、それらしい報告をしてね」と結んだ。
その後、社長にこの突飛な話の本意を聞かなかったので真相は闇の中だ。世間では、3年以内の離職率が高いという。多分、離職を防止する策の一環だったと思う。が、向上心の強いネヲンの性格を刺激して、2日も仕事をすればいいという「エサ」をぶら下げて、もう一つの仕事(セールス)を与えたのかもしれない。
東京のおばあちゃん
ネヲン、初めてのセールスが東京でスタートした。セールス期間中の宿泊先は、熱川の旅館を、現・社長に譲り世田谷の経堂の戻ったおばあちゃんの家である。おばあちゃんは、お手伝いの静さんという南伊豆出のおばさんと二人で暮らしていた。

初めてお目にかかったおばあちゃんは、80歳を超えたその顔にはシワもなく総白髪が魅力的だった。そしておばあちゃんは、夕食のお膳を前に、ネヲンの顔を見つめ、「あなたがネヲンさんという方ですか」と、やさしくかたりかけた。
「そ~ですか、あなたがネヲンさんですか」と、ゆっくりと頷きながら、
「お父ちゃん(社長)は、ここへ来るたびにあなたの話をするんですよ!」と続け、
「あなたは、お仕事に一生懸命な方だそうですね。お父ちゃんは大助かりだといって、それはそれは感謝しているんですよ」と、思いもよらないことをいった。
さらに、「これからも宜しくお願いしますね。お父ちゃんは、とても期待していますよ!」と、頭を下げながら丁重にいった。
ネヲンは返答のしょうがなくて、ただ黙って聞いていた。初対面で、しかも、高齢のおばあちゃんに頭を下げられて、ネヲンは、ますます仕事に励もうと思った。と同時に、この婆さんは妖怪か? という不謹慎な思いもよぎった。
この居心地のいい家も、翌年の春、三番目に生まれた社長の長男が中学校へ行くために住まうことになった。そんな訳で宿泊先はネヲンの実家に移った。
この頃になると、テレビや雑誌のおかげで温泉旅館にも陽が当たるようになり、実家の父母たちの温泉旅館に対する拒絶反応も薄くなったので助かった。内緒の話だが、会社から支給され宿泊料は、すべてネコババして小遣いにした。
時代背景
ネヲンがセールスを始める10年ほど前から、旅行斡旋の仕事は、大きな駅周辺にある大手旅行会社が独占していたが、中小零細な旅行会も私鉄の小さな駅前にまで看板を上げて食い込み始めた。

旅行会社の主な業務は、ホテル・旅館や交通機関の手配と、パッケージツアーの販売などです。だが当時は、看板を上げたばかりの中小零細な旅行会社には、手配する先のホテル・旅館などの情報が著しく不足していた。

のんびりお茶
そんな時代に、各地の有名旅館は次々と東京に直営の案内所を開設した。こんな時代は、東京案内所の所長さんは先駆者利益を満喫していた。すなわち、昼まではスポーツ新聞を片手にお茶をして、ランチが済むと、さてと、腹ごなしにと旅行会社を4~5軒回れば、お客さんはいくらでも獲得できたからだ。
残念ながらネヲンがセールスを始めたころは、街の旅行会社には旅館のパンフレットがほぼ行き渡っていた。なので旅行業者は、それぞれが独自で旅館手配のネットワークを構築していた。すなわち、パンフを持ち歩くだけで濡れ手に粟という時代は終わっていたのだ。
また、街の旅行業者の手元にあるパンフは、当然、営業活動をした旅館のパンフだけだ。その中に入っていないホテル アタガワは、いわば無名同然の旅館であった。
こんな時代背景のなか、いわば社長の思いつきのように始まったネヲンのセールス、まわりの誰も手ほどきをしてくれなかった。また、見えないオバケに怖さを感じないネヲンは、セールスに対する不安がなかったので誰にも教えも請わなかった。
ネヲンのセールスに対する知識といえば、これまでに見聞きした、地図を頼りに旅行会社を探し当て、そこで、「お願いします」と言いながら旅行業者にパンフを差し出すといったものだった。そんなわけで我流セールスがスタートした。
セールスを始めた
朝、ネヲンは熱川温泉と書かれた売店の手提げ袋にパンフレットと地図を詰め込んで出かけた。経堂の駅に着くころには、両手のひらが ” J の字 ” になっていて、うまく切符が買えなかった。営業とは力仕事だと思った。
いつも楽をしようとするネヲン、パンフレットの重さから逃れる方法を考えた。三日目の仕事終わりにリュックサックを買おうと新宿でデパートに立ち寄った。
が、そこには本格的な登山用のリュックしかなかったのであきらめた。まだこの時代には、リュックというと、ヤミ米を運ぶものというイメージが強く残っていた。
社長は、おばちゃんから情報を得たのか、ネヲンが嬉々としてセールスをしていることを知って、なんとなく経理 兼 セールスの担当となった。
これって結構大変で、毎月曜日の朝、熱川からセールス先の東京へ向かい、帰宅は金曜日の夜であった。そして土曜日は宿直。たまっている経理の仕事は合間にこなした。セールスが休みなのは、週の中ほどに赤い日があったときだけだ。
そして、名刺交換のマナーさえ知らないネヲンは、セールス活動を馬力だけでこなした。セールス先では店主に直進し、ただひたすら、「お願いします」と言いながらパンフを差し出した。圧倒された店主は黙ってパンフを受け取った。ネヲン、パンフを手渡すと相手の顔色も見ずにすぐに退店した。
いやはやなんという無知で無謀な挑戦なんだろう。
苦あれば楽あり
人間は動きまわると体力だけでなく知恵もつく。朝、ネヲンは電車に乗ると一番に渋谷や池袋などの巨大ターミナル駅を目指した。駅の周辺には旅行業者が密集していたし、地下コンコースには、パッケージツアーのパンフレットを並べた屋台のような小さな旅行会社が並んでいたから、重いパンフレットを半減させられた。

美味しいランチの宝庫
駅の地下街は薄暗く雑然としていたが、仕事以外にもう一つの楽しみがあった。飲食店が軒をつらねていてランチが格安で食べられた。一人セールスなので、混雑を気にせずいつでもどこでも簡単にもぐり込めた。多くのビジネスマンの舌に鍛えられたランチは、どこでなにを食べても美味かった!
そして食後は地上に出て、冷暖房完備の証券会社にもぐりこみ、株価の放送を聞きに来た客のふりをしてフカフカの椅子に座ってネヲンはひと眠りした。パンフが半減した午後は、電車も空いてくるので気分も軽くなった。
大都会に夏が来た
ネヲンは、夏に背広を着ている人は「気が狂っている人」だと思っている。一説には、ワイシャツは下着なんだから、下着で外をうろつくなんて恥ずかしいだろうという。また、半袖のワイシャツ着用なんてあり得ないという。

ネヲンは夏が来たら、旅行業者のお叱りが多くなった。半袖のワイシャツ姿のせいかもしれない。また少し余裕ができたので、突撃型セールスから、店内で一呼吸置いたから目ざわりだったのかもしれない。ネクタイがダサい、靴が汚い、床屋へ行け、挨拶の仕方や店の出入りがなってないなどなど、苦言をタップリといただいた。
当時は、「週刊少年マガジン」に連載された漫画「巨人の星」が大人気だった。父・星一徹の「ちゃぶ台返し」、オヤジの権威が絶大だった時代である。

御徒町駅のガード下
夏のある日、半袖のワイシャツに水色のネクタイという身なりのネヲンが、御徒町駅のガード下の旅行会社の店頭に立った。狭い店舗の奥に仏頂面のオヤジがいた。
訪問の挨拶と同時に、「背広はどうした!」と、きつい声が突き刺さすように飛んできた。
カチンときたネヲンは、客もくれないのに文句だけいうなと思い、黙ってそのまま店を出ようとしたら、「ちょっと待て」と、呼び止められて、オヤジのありがたいお説教を延々と聞かされた。この「御徒町のオヤジ」の後日談はのちほど…。

おかあさん
それは、大井町駅前のアーケード街の中ほどにあった「青空観光」の女性店主である。そこは、観葉植物の鉢が並べられた爽やかなカフェのような雰囲気であった。
ネヲンと同時に、汗をふきふき若者が入ってきた。汗で濡れた背中にワイシャツがべったりと張り付いていた。
二人の会話から容易に親子だと察しられた。二人の短い会話のあと、オレを見る店主(おばさん)の目に、今までのおじさんたちとは違うものを感じた。汗だくで帰ってきた息子と、うだつの上がらなそうなネヲンがダブったのであろう。このあとネヲンは、このお店から初めての団体客をもらった。お母さんが同情してくれたのだ!
秋が来た
秋の旅行シーズンが到来した。この時代のホテル アタガワには人的な余裕があったので、社長は何か魂胆があったのか、ネヲンにそのままセールスを続けさせた。

秋は旅行業者のかき入れ時だ。特に個人業者は添乗業務などでフル回転していた。忙しすぎるのか、みんながイライラしていた。そのとばっちりがネヲンにきた。
パンフレットに現地旅館の電話番号が記載されているのが気に入らず、「お前の旅館は、直接お客さんを取ろうとしてるのか」と、本気で怒りながら、即、パンフレットをゴミ箱に打ち捨てた旅行業者もいた。
また、「熱川温泉のホテル アタガワです」とパンフを差し出しながら元気よく挨拶をすると、「うちは、熱川館と大和館しか送客しないので、パンフはいらないから持って帰れ」と、一蹴されたこともある。二流旅館の哀しさを思い知らされた。
怒る人たちの多くは、駅ちかの旅行業者のおじさんたちだった。この時代はパワハラなどという思考がなかったので、オヤジたちは何を言ってもよかった。むしろ、怒るオヤジはほうが、いいオヤジだと思われた時代だった。
賢い人は、失敗を糧に振る舞いを改めるが、ネヲンは、オレはオレだとマイペースをつら抜いた。それは、朝から晩まで怒られていたわけではないからだ。
他人のことを考える余裕も出てきた。ある旅行会社を尋ねたら、年輩と若い女性の二人にネヲンは完全に無視された。そこへ、「栃木の一流旅館です」と言って、二人ずれの青年がさわやかに入店してきた。すると女性たちは破顔一笑、邪魔者を排除するかのよう、「どうぞ、どうぞ」といって奥へ招き入れた。
青年たちは、それなりの競争を勝ち抜いて一流旅館に就職した。なんの苦労もせずに今があるネヲンとの待遇の違いは当然だと思う。が、ネヲンは余計な心配をした。こんなセールスをしている青年たちが、将来、名刺を失ったときのことを。
ネヲン、たくさん怒られたが、それは自分にも非があったので苦ではなかった。しかし、無視されるのは人間性を否定されたようでやるせなかった。
あゝ上野駅
ネヲン、セールスをはじめて半年が過ぎた。旅館のセールスは、物品の販売と違って、将来発生するだろうお客さんに対する働きかけを旅行業者にするものだから、すぐに結果が出るものではない。しかし、近頃は成果のことも気になってきた。

ここは上野駅である。疲れはててネヲンがホームのベンチに座ると、目の前では次々と電車がすべり込んでは出ていく。そのたびに大勢の乗客が乗り降りをする。電車が発車ると、ホームは一瞬ガラガラになるがすぐにまた乗客であふれる。
こんな繰り返しをぼ~っと見ていてネヲンは空想する。このうち、たったの一車両分の乗客でいいから、毎日、オレの客になってくれたらいいのにな~と思っていると、いつのまにか眠りこんでしまう。上野駅のベンチで居眠りなんて最高!
見捨てない神もいる

木枯らしの吹きぬける晩秋の夕暮れ、ここが最後の訪問と決めて小さなバス会社も兼ねる旅行会社に入店した。奥で二人の男性が何やら難しそうな話しをしていた。

命拾い
「熱川温泉のホテル アタガワです」と、ネヲンは相手の事情など無視して、大きな声で訪問の挨拶をした。
「ああ、そこへ資料を置いといて」との、そっけない言いようで、年配で体格のいい男性が、こちらにチラッと顔を向けて返した。
その言いようにネヲン、突然、えたいに知れない感情がこみあげてきて、
「わざわざ熱川温泉から出てきているのに、話も聞かずにそこに置いておけとはなにごとだ」と、あろうことか逆ギレをして大声を出してしまった。すると、年配の男性が、「まあ、まあ、」と、いいながら慌ててとんできた。
「捨てる神あれば拾う神あり」というのがある。頑張っているネヲンを神様は見捨てなかったのか、こんなネヲンは事なきを得た。「捨てない神」がいたのである。ネヲンを助けてくれたのは、ここの社長であった。
再び御徒町駅のガード下
人々が慌しく行きかう師走のある日、ネヲンは、あの御徒町駅のガード下の旅行会社を訪問した。今回が5度目である。2回目と3回目は完全に無視された。4回目は、「なんだまたオマエか、煩わしいから来るな」と言われた。
何度も顔を出したのは、同じお叱りでも、ここの店主のそれは他と少し違うと感じたからだ。5度目の今回は、「まあ座れ」と店主は、狭い店舗の片隅に小さな丸椅子を出した。そして、ネヲンの顔をまじまじとみつめ、「目つきが変わったな」と言った。
この店主の前職は、房総の大きな旅館の支配人だったという。あの日の苦言は、ネヲンへの顔を一目見て、なぜか支配人時代に戻ったからだそうだ。
そして、「あの日のオマエのセールス姿を見てこれでは苦労するだけだ。むしろ、現地での番頭さん生活のほうがオマエには向いているように見えた。だから、セールスなんかやめて現地に帰れといったんだ」と、あの日の話をした。
ややあって、「今日はお客さんを決めてやるから付いて来い」と、言って突然席を立った。訪問先は、工場の敷地内に建つプレハブの2階にある社員用の休息室だった。年季の入ったテーブルを前に中年の幹事さんが3人で待っていた。
御徒町のオヤジは、「今年は海方面の旅館がご希望でしたね」と言い、手提げバッグから三部のパンフを取り出し、舘山寺、熱川、鴨川の順に机上に並べた。
左右の旅館は明らかに格上だ。それを見たネヲンは、オヤジの真意を図りかねハラハラドキドキした。そして帰路、オヤジから、「お客さんの希望で、お前の所に決まらなかったな、悪かった」と、言われることを覚悟した。
御徒町のオヤジは、幹事さんが思い思いにパンフを手にしたのを確認し、まず、舘山寺のパンフを手に持って、「ここまでは距離があるので渋滞にはまると悲惨です」と言い、そして、鴨川の旅館は、「ここは、私がいたところなのでおすすめですが、宿泊料金が高めなので宴会費を削らないといけませんね」と続けた。
そして、御徒町のオヤジは幹事さんの顔色を見ながら、この2部のパンフをさりげなくバックにしまい、熱川のパンフを指差し、「ここなら料理もいいし、芸者の数も飲料代も心配いない。さらに、お部屋から波の音が聞こえるほど海に近い」と説明した。
この話は熱川であっさりと決まった。帰りの道すがらネヲンは、
「なんで、当館以外のパンフを並べたんですか? それも明らかに格上の旅館のパンフを2部も。当館が真っ先に外されると緊張し冷や汗が出た」と、口をとがらせてガキのように言った。二流セールスマンのネヲンは環境(一流旅館)への不満を漏らした。
さらにオヤジの返事も待たずに続けた。
「なんで当館が目立つように格下の旅館じゃなかったのか」と、食い下がった。
「オマエは本当に頭が悪いな~」と、オヤジは口悪く言って、
「熱川のパンフだけだと、『ほかに候補はないのか』と、言われたら厄介なことになるだろう。そんなことも分からないのかバカ!」
「それに、ボロ旅館ばかり3軒も並べたら、『オレたちを貧乏人扱いするのか』と、お客さんが怒り出すだろう」と言って、「オマエは本当にバカだ」とダメ出しの一言。
そして、「両端がよければ、お客さんは勝手に真ん中も同格だと思うだろう」と、御徒町のオヤジは結んだ。それを聞いてネヲン、目からウロコ!
頭のいいひと
本当に頭のいい人は、「自分で考えろ」だとか、「寝ないで仕事をしろ」なんて理不尽で断片的な言い方はしない。話の道筋は適切で分かりやすく言って聞かせる。
教えて!
ネヲンは間もなく30歳になる。でも、3歳児のようにどこでも誰にでも、「なぜ?」「どうして?」「教えて!」と、問うことができるいい性格を持っていた。
このあとネヲンは、セールス先でよく怒られる。いいセールスマンになるにはどうしたらいいのかと御徒町のオヤジに素直に聞いた。
「人間の多くは、怖そうな人を見ると本能的に避ける。しかし、コイツは反撃しないと知れば言いたいことを言う、だから、怒られたことを気にすることはない。むしろ気をつけるのは何も言わない人だ。多くは、無関心だから何も言わない。が、コイツには何を言っても無駄だと思っている人がいることを知れ!」
「要するに、利口な人に馬鹿と思われるのが最悪だ。よく相手の表情を読め」と、
教えてくれた。こんなありがたい話が「教えて!」の一言で聞けるネヲンである。
さらに、教えて!
そして、「いいセールストークとは、なんですか?」とネヲン、続けて聞いた。
「旅館の説明的な話を長々としないことだ」と、御徒町のオヤジが言った。
「えっ、仕事熱心がいけないのですか?」と、ネヲンが口をはさんだ。
「どうでもいいことを長々と説明してる奴は、自己陶酔しているだけで、相手のことをなにも考えない無神経なヤツだから、こんな奴が一番嫌われる」と、オヤジ。
「旅行業者の仕事は、ぼ~っと一日、お客さんが来るのを待っているのではない。やることがいっぱいあるんだ。その仕事中に、どうでもいい旅館が日に十数軒もくる。そのたびに仕事の手を休め席を立たなければならない。こう言われればアホなオマエでも想像がつくだろう」と、続けて一呼吸置き、
「忙しい時のオレは、うだうだ言ってる旅館のヤツが帰ると同時に、パンフなんかゴミ箱へぶち込む。オレだけではない旅行業者はみんな同じだ。ウソだと思ったら、セールス先で機会を見てゴミ箱をのぞいてみろ。パンフがいっぱい入っているから」と言って結んだ。オレのセールス結構いいかもとネヲン思った。
人間って不思議な縁で結ばれている。その後、この店主には、セールスのことや現地での仕事のやり方などをいろいろと教えてもらった。そして、この御徒町のオヤジの口癖は、「仕事は、考えながらやれ」であった。
また春が来た
熱川温泉にまた春がめぐってきた。そして、騒がしかった春の旅行シーズンが過ぎようとしていた。お客さんが少なくなると、静寂を破るものは寄せては返す波の音だけである。目の前には、伊豆大島がゆったりと横たわっていた。

社長の思惑通りネヲンは踊った。社長は、まんまと一人分の給料を浮かせた。ネヲンはといえば、たいした成果もだせなったが、給料をもらいながら、きびしい営業の学校に通っているのだと思っていた。社長とネヲン、どちらもしたたかであった。
教育・訓練とは
思い起こせば、自分で蒔いた種(我流でセールス)とはいえ、セールス先では、罵倒され、蹴とばされ、無視され続けたが、新しいことへの挑戦は楽しかった。ネヲンが、こんな日々を苦にしなかったのは前職の自衛隊での経験のお陰である。

大型トラック
助教に、「さあ、動かしてみろ」と言われ、運転席に座らさられる。エンジンをかけると、ブルンと大きな音がして車体がガタガタと揺れた。
目の前には、大きなボンネットと空があるだけであった。はるか先に景色があった。
訓練が始まり、棒のような長いシフトレバーを操作して、ダブルクラッチでギアチェンジをするなんてオレには絶対に不可能だと思った。ギアチェンジがうまくいかなと、ガリガリと歯車が欠けるような大きな音がした。
大型免許とけん引免許を取得する三か月間は、操作をあやまっり、うまくできないと助教に指揮棒でヘルメットをたたかれ、広い駐屯地を走らされた。
そして、「指導を受ける」とは、怒られることと耐えることと己の努力であることを知った。でも、よく考えたら「0円」で教えてもらっているのだ。タダどころか給料までもらっている。寝言を言っていたらバチが当たる。
セールスの総括
ネヲン、人生初めてのセールスを総括した。結論は、都内の中小零細の旅行会社へのセールスを止めることにした。理由は、都内はすでに有名な温泉旅館の東京案内所がしっかり営業基盤を確立していたし、ネヲンのように非力で、そのうえ二流旅館では入り込む余地がなかったからだ。
では、どうする?
最大手の旅行会社「JTB」にアタックすることに決めた。「オイ、オイ、なんて無謀なことを…」と、いう声が聞こえそうであるが、心配はご無用!
JTB、NTA、KNTなどの大手旅行会社には年間を通して「部屋提供」をしているので、それなりの実績もあり知名度もあるから、食らいつく余地があるはずだと考えたのだ。「坂の上の雲」、明治の日本人はロシアに戦いを挑んだではなか。
ネヲンは、なにごとも自分に都合よく考えるタチである。JTBから効率よく集客するには、団体旅行専門の支店にセールスをかければいいと安易に考えた。そんなわけで、JTB有数の団体支店である「JTBの団体旅行渋谷支店」に行くことにした。
JTB団体旅行渋谷支店にて
国内最大級の団体旅行の拠点である JTB団体旅行渋谷支店を攻略するために、ネヲンは、無謀にも、あっと驚く大胆な行動をおこした。

その日の朝、ネヲンは一人、JTB団体旅行渋谷支店が入るビルの裏口に立った。大都会のビル群の表通り側は綺麗であるが、ひと気のないビルの裏側は寒々としてギャング映画の舞台のようである。ネヲン、大仕事をまじかにひかえプレッシャーは感じたが、気持ち的には落ち着いていた。
開店時間の30~40分前になると、ポツリ、ポツリと社員が現れた。余裕をもって出社してくる社員達は、勤務中の顔とは違って穏やかな顔をしていた。
「お早うございます。伊豆のホテル アタガワです!」と、大きな声を掛けながらパンフレットに名刺をそえて差し出すと、どの人も軽く会釈して素直に受け取ってくれた。なかには、「ありがとう」とか「ご苦労様」などと、声を返してくれる人もいた。さすが JTBのみなさんは、紳士、淑女であった。
「な~んだ、簡単じゃん!」と、この時は軽いのりで鼻歌まじりのネヲンであった。
が、15分も過ぎると社員達がゾロゾロと列をなしてやって来た。ネヲンにとっては想定外である。さすがは大所帯の JTB団体旅行渋谷支店の出社風景であった。

こうなるとパンフを手渡すだけで、ネヲンは、いっぱい いっぱいになってしまった。名刺など添えるいとまがない。また、挨拶のほうは「お早う…」とか「ホテル…」とか、とぎれ とぎれになって、自分でも何をやっているのか解らなくなってしまった。
このあわただしかった時間は、アッという間に過ぎ去った。ネヲンは、ホッとひと息入れつつ、支店が入ったフロアーの入口の前で営業開始の時間をまった。
ネヲンは、気を落ちつかさせながら手配係りや営業さんへのこれからのセールス方法などを、無意識のうちにシュミレーションをしていた。そして、思ったより簡単にことがはこんだのでチョット有頂天であった。
思いもよらないこととなる
業務開始の時刻になった。すると、女子社員がでてきて「ミーティングが始まりますから…」といいながら入口のドアを閉た。ネヲンは「どうぞ」といいながら身を少しずらせた。このときは、まだ成功の余韻が残っていて気持ちに余裕があった。

再びドアが開いた
ややあって、ネヲンを奈落の底へつき落とす入口の扉が開いた。先ほどの女性が、「支店長が呼んでますから」といって、ネヲンをフロアー内に招き入れた。このときネヲンに、得体のしれない緊張が走った。
女性のあとについて恐る恐るフロアーに入ると、そこでは全社員が起立してミーティングをしていた。
全員の目が一斉にネヲンに注がれた。突然、大量のフラッシュを浴びせられたようで、頭の中がクラクラとしてなにがなんだか解らなくなった。
支店長のとなりに並ぶようにと女性が促した。何だ! 何だろう? セールス経験の浅いネヲンは、超弱気になって、ドキドキしながら支店長の隣におずおずと近寄った。
「5分間あげるから、あなたの旅館の宣伝をしなさい!」と、支店長がいきなり言った。ネヲン、ドヒェーッ、マジか!? と、予想だにしない支店長のひと言に、慌てふためき、脳内は大混乱で心臓がバクバクした。
折角、清水の舞台から飛び降りる覚悟でパンフ配りをし、大きなチャンスをつかんだといのに、ネヲン、すべてが我流のセールスの未熟さと、御徒町のオヤジの教えを実践できない頭の悪さが重なって、まともなプレゼンができなかった。
自分の旅館の欠点ばかりを並べたてて、こんな旅館ですが、よろしかったらご送客くださいと、やってしまったのだ。心やさしそうな人がパラパラと拍手をしてくれたが、ほとんどの社員達は、「そんな旅館に、お客さんなんか送れるか、アホ!」という目でネヲンを見ていた。
このときネヲンに支店長を見やる余裕があったら、こんなダメ男のために貴重な時間を無駄にされたと苦虫を潰したような顔の支店長が見えただろう。
その後、どのようにして支店を退出したかの記憶がない。気がつけば、道玄坂のビルの合間の天を仰いでいた。青空に白い雲がポッカリと浮かんでいた。その雲が、我がホテルの支配人の顔のように見えた。
天才がいる

世の中には「人間関係構築」に必要なスキルを、すべて持って生まれた人がいる。ネヲンの上司・ホテル アタガワの支配人は、たった一晩、酒の席を同じくするだけで完全に人間関係構築してしまう天才である。
そんな支配人を目の当たりにしたネヲンは幸運である。ネヲンは、自分が結果を出すには、アリのように這いずり回るしか方法がないと悟れたからである。

ギンギンギラギラ
この支配人の宴会芸は、一瞬で観客を虜にしてしまう。ある時の社員忘年会でその芸を披露した。
童謡「夕日」の、ぎんぎんぎらぎら夕日が沈むに合わせて、お相撲さんが四股を踏むような格好で、両手をひらひらさせて夕日が沈む仕草をしてみせた。
ネヲンたち一同、一瞬沈黙、そして拍手喝采、大爆笑であった。一流の仕事人になろうと思えば、いいものとか、素晴らしいことは直ぐに取り入れるべきである。ネヲン、この支配人の十八番、ぎんぎんぎらぎらの伝授を受けなかったことを悔いた。
もし、JTB団体旅行渋谷支店の支店長に「5分間あげるから、あなたの旅館の宣伝をしなさい!」といわれた時に、ぎんぎんぎらぎらとやっていたら、ネヲンは、末永くJTBで語られる伝説のセールスマンになっていただろう。クソ~!
大手旅行会社は、凄い!
これまでの JTBは、全国の支店で発生した予約や取り消しを、東京の手配センター経由で、直接それぞれの旅館と電話でやり取りをしていたが、あるとき JTBは、こんな業務を一変させた。

予約や変更、取り消しの電話に代わって、深夜 0時になるとテレックスが、強烈な機械音をたててヘビのように長い「さん孔テープ」をはきだした。そのテープには暗号のような穴があいていた。それを読み取り機かけて、日本語の文書に変換した。
同時に、店舗での旅館手配用の資料が整備された。各旅館の部屋タイプや眺望、料理の内容、温泉の効能や風呂の大きさ、露天風呂の有無などの詳細な情報はもちろん、温泉街の歩きかた地図や付近の観光地などが余すことろなく記載されていた。
それに伴い、全国の温泉旅館は、それぞれの温泉地内で個別に、01、02、などと格付け的な番号が付与された。その番号は、JTBの社員たちが旅館を販売する際の選択基準となった。ちなみに、ホテル アタガワは「06」であった。
この「06」という番号は、6番目に申し込んだお客さんがホテル アタガワに送客されることではない。上位の 01~05番の旅館が満室になったら送客の順番がまわって来るということだ。ただ待っているだけでは、お客さんは来ない。
これらのシステム化で、宿泊クーポンや電車のきっぷなども瞬時に発券されたので、窓口業務も清算業務も簡素化された。よって、経験のあさい社員でも、お客さんの要望通りの旅館がいとも簡単に販売できるようになった。
この業務システムの強化は、店頭販売員たちの労力を削減したが、同時に、社員たちを金太郎アメ化し、現地の情報提供者である旅館のセールスマンのやる気をそいだ。
JTBの支店にて
JTBの社員は、街の旅行業者のような厳しい応対と違って、どこでも誰でも柔和に接してくれるがそこでストップしてしまう。その先の関係が構築できないのだ。口悪くいえば、「クソ真面目な奴等」と「融通の利かない奴等」ばかりだからだ。
暖簾に腕押し、取り付く島もないというやつである。一番始末が悪いのが無表情で、「ハイ、わかりました」と、オウム返しのように連発するヤツである。

モールス信号発信用 電鍵
ネヲンの悩みの解決のヒントは、またしても自衛隊での体験だった。そこは前期の新隊員教育が終わり、実務遂行の技能を習得する後期教育の場であった。
始業の朝、若い教官がテープレコーダーを回しモールス信号を流した。ネヲン、それが雨だれの音にしか聞こえず、これは大変なところに配属になったとビビった。
そして、がり勉タイプの若い教官は、背後の黒板に「塙 保己一」と書き、この偉人とは関係はないが、小生の名は「ハナワ」ですといった。続けて、知っての通り塙 保己一は江戸時代に活躍した全盲の学者です。諸君は若くて五体満足な青年たちだ、頑張れば何でもできると風貌通りの言い方をした。
--・・・-・-・---・-・・-・・・・--・---・-・・・---・--
三か月後、30数名の隊員たちは、上記の長音と短音が連続したモールス信号を、「奮励 ( ふんれい ) 努力 ( どりょく ) せよ」と、「解読」できるようになって、各地の駐屯地に配属されて行った。
解読なんて暗号解読みたいだが、モールス信号には、拗音(ようおん)の「ょ」がなく「よ」と同じ -- なので、文面から判断しなくてはならなかったからだ。
JTB新宿西口支店にて

新宿駅西口は、奇しくも大学卒業時に受験した安田生命の本社があるところだ。入社試験で、「ここは、あなたようなダメ学生の来る会社ではない」と、はっきりとダメ出しされた場所であった。が、今回は成功の入り口になった。

セールスの神様がほほえんだ!
いつものようにカウンターセールスをしていると、傍らの若くてやんちゃそうな社員がネヲンのパンフをチラッとみて「お客さん入れたよ!」とボソッと言った。
ネヲン「有難う御座います!」と言いながら、その若者の顔を見て閃いた。成功の扉がいきなり開いたのだ。
ネヲンは、就職希望企業ランクで常に上位の JTBだから、全員が優秀だが、性格までは同じではないことを、このとき知ったのだ。少数であるが、会社の指針やシステムにしばられない社員がいることを知った。ネヲン、JTB攻略の糸口を見つけた。
「そうだ!」オレのように販売能力の低いヤツは、売りつける努力よりも、買ってくれる人を探せばいいのだと気が付いた。セールスには二種類あったのだ。
「売るセールスと買ってもらうセールス」だ。だから、自分のタイプが分かれば、セールスって結構気楽な職種である。ありのままに振る舞えばいいからだ。
ネヲン、今までのセールススタイルを変えることにした。JTBの店舗に入ると、まず、カウンターにいる社員たちの顔つきや服装、動きを、少し離れたところからそっと観察した。そう、アウトサイダー的な社員を見つけることから始めたのである。
JTBの社員が任意で旅館の手配をしも、それは規律違反ではない。社員たちには、お客さんの希望があれば、それを優先できるという決まりがあったからだ。
さて、この戦術はみごとに当り送客が増えた。そして、思わぬ波及効果もでた。これまで、JTBと旅館を結ぶのはテレックスだけであったが、「ネヲンさんいますか」と、JTBの社員からじかに宿泊依頼の電話が入るようになったからだ。
旅館の仲間たちは、天下の JTBから名指しの電話が入ることを評価してくれた。でも、曲がりなりにも、ネヲンが成果を出せたのは、社長の指示(?)に従わず、3日間遊ばなかっただけである。ただ、やみくもに歩いただけであった。
さてさて、この新宿西口支店には後日談がある。総案を起業したネヲンが下呂温泉に宿泊した時のことである。その旅館には、ネヲンがこの支店に出入りしていた時代に、この支店で勤務していたという元・JTBマンが支配人をしていた。
この支配人は、見るからに真面目一本槍というタイプだった。残念ながら、ネヲンの選別からは漏れていたので、お互いに、「ヤァー、ヤァー、あの時は」といって、昔話に花が咲く再開ではなかった

「ゲロオンセン」の名の由来には諸説あるが、最近では、下呂温泉にはカエルの神様が祀られていて、「ゲロゲロ」と鳴くカエルの声と「下呂」が掛けられているという説が有力であるという。そこには、若返る(カエル)、無事帰る(カエル)というご利益もあるそうだ。
JR高山本線「下呂駅」は、下呂温泉の最寄り駅です。下車せずに高山方面に向かった 3つ先には、「上呂(じょうろ)駅」がある。もしやと思って地図で調べたら、「中呂」という地名もあった。飛騨川の上流から、上呂、中呂、下呂という順にある。
JTB蒲田支店にて
ネヲンは、JTBの支店でのセールスのコツをつかんだので少し余裕がでてきた。この日は、人情喜劇「蒲田行進曲」で有名な蒲田にやってきた。JTB蒲田支店は、活気はあるが新旧が入り混じって雑然とした蒲田駅近くにあった。11月も下旬になってこの街にも木枯らしが吹いていた。なぜか、木枯らしが似合ってる感じがした。

ネヲン、例によってまず店舗の片隅で JTBの社員たちの動きを見ていた。余裕とは恐ろしいもので、ローカウンター越しに会話している管理職風の年輩社員とブレザー姿の若い二人連れのお客さんとの雰囲気があやしいことに気が付いた。
年輩の社員は、売り上げよりも何よりも、煩わし仕事にかかわりたくない様子がありありでめんどくさそうに応対していた。
ネヲンは、その席の隣の社員をめがけて立ち上がり、うまく接触し、パンフを広げながら隣の人たちの会話に耳をそばだて、広げられている企画商品を盗み見た。
会話の内容が掴めた。忘年会パックの20名様以上が問題になっていた。はなからやる気のない JTBのオッサンは「規定が…」の一点張りである。お客さんは、一班で15~6人の班が幾つもあるから、「そこを何とか…」と、食い下がっていたのだ。
交渉が決裂するとみたネヲンは、早々にセールスを切りあげ、店外で2人連れお客さんにアタックしようと思った。店舗の前には蒲田駅につながる歩道橋があった。歩道橋のうえからは店舗への出入りが丸見えである。ネヲンは、お客さんを見逃さないように人の動きを確認しつつ木枯らしに耐えて待った。

二人の若者が歩道橋を登って来た!
ネヲンは、「JTBでのお話を隣席で聞いていました」と断りをいれパンフと名刺を差し出しながら、ホテル アタガワの忘年会パックのチラシを手渡した。「寒いね!」と、言いながら若者たちに、旅館にとってはおいしいコンパニオンパックの説明をした。
この話はこの歩道橋上であっさりと決まった。
若者たちも目的が達成され、ホッとして笑顔を見せた。
この若者たちは、全日空の羽田空港の地上勤務者で作る労働組合の役員であった。15~16人を一班として、10班でローテイション勤務をしていた。自分たちの班だけではなく、仲のいい人がいる3つの班の来館も確約してくれた。なお、残りの班の人達には我々の結果を見て、よければ次の機会に必ず紹介するとの約束までしてくれた。
ちなみに、ネヲンが必死に捕まえたお客さんの対応に粗相があるはずが無い。当然、若い人達は喜んで帰り、残りのグループを次々と紹介してくれた。
蒲田と伊豆は、旅行距離も丁度いい。忘年会の時期がくると、毎年、つづけて来てくれた。そして、何人かは、新婚旅行で来てくれた。
さらに、オマケもついた。ネヲンに対する社長の評価があがった(?)のである。全員集合の席で、「あれはど不愛想だったネヲンさんが、お客さんのまえでニコニコするようになった」と、人は変われることの例え話として取り上げた。
蒲田のさくら咲く

さらに、話は続く。
この若者達は、全日空「健保組合」の保養所指定に努力してくれた。健保組合への訪問とはいえ、全日空の本社ビルに出入りできるのはとても気分がよかった。そこでは、組合員の旅行だけではなく、北海道からきている女中さんたちの無理難題な航空券の問題まで解決してくれた。蒲田で、さくらが満開となった。
パンフレットスタンド
JTBのそれぞれの支店内で、いわば組織内の異分子的な社員たちにアタックしたネヲン、多少の成果は出しが、これではただ取り組んだけだ。この程度では、大きな獲物に食らいついた意味がない。大きな獲物には、それなりの見返りがあるはずだ。
だからと言って団体客は、団体旅行渋谷支店での結果のとおり期待はできない。ではどうする? 御徒町のオヤジの顔が浮かんだ。考えろ、考えろ! と、言っている。
JTBは、手配旅行だけではなく、北海道、沖縄などといったパッケージ旅行商品や宴会パックやグループ旅行などの企画商品も販売している。ネヲン、このあたりで何かを見つけて JTBの組織に乗っかろうと大胆なことをたくらんだ。
ネヲン、そんな魂胆を秘めて店舗に入った。今回は社員ではなく、何かヒントはないかとあたりをキョロキョロとみまわした。そこで目に留まったのがパンフレットスタンドだった。パンフレットスタンドには、パックツアーの冊子や、「ペラ」と呼ばれる A4サイズの一枚物のチラシが、ぎっしりと差し込まれていた。

ネヲン、これにヒントありとひらめいた。仕事に熱を込めているときは、いつも神様が応援してくれる。不思議といえば不思議だか、当たり前といえば当たり前だ。
設置スタンドから適当なペラを一枚とり出して、これの製作部署はどこだ? 発行責任者は誰だ? この管理者はだれ? と、いろいろと考えながらながめまわした。
すると、裏面の下のほうに「JTB東京営業本部」と小さな字で印字された一行が目にとまった。これだと察したネヲン、さっそく顔見知りの社員に「これって、このパンフを制作・管理しているところ?」と尋ねると、答えは予想通り「そうですよ」であった。彼は、親切にもすぐに JTB東京営業本部の所在地をメモしてくれた。
JTB東京営業本部
東京営業本部(以下、東京営本)は台東区の上野にあった。街は、上野公園の桜が満開となり、パンダ人気もともなって大賑わいであった。「犬も歩けば棒に当たる」というのには、幸運説と災難説があるそうだが、ネヲンには幸運の棒に当たった。

幸運の棒とは、東京営本で梨本課長と出会たことだ。この課長、背丈はやや低いが、ガキの頃は仲間とともに野山を駆けずり回っていただろうな、という印象の風貌であった。社内では梨本三兄弟として有名で、二人の兄は、北関東管内でそれぞれが支店長として活躍していた。
梨本課長は末弟らしく気さくで、ネヲンのストレートな物の言い方が気に入ったのか、「ネヲンちゃん、ネヲンちゃん」といって、いつも可愛がってくれた。
そんな課長が、ある日、旅館の人たちが度肝を抜く、酒10本付または5本付という「十兵衛さん五右衛門さん」という宴会用の企画商品を作成していた。この企画のお銚子は一定の比率で、ビール、ジュース、ウイスキーとの交換が可能で、比較的小規模の旅館が主体でよく売れた。
「オマエのところも参加しろよ」と、ネヲンの顔を見て誘ってきた。
「これじゃあ儲からないからイヤだ! 酒1本付ならいいよ」と、ネヲンは答えた。
「バカヤロー、この企画でそんなこと出来る訳ねだろう~」と、JTBの社員らしからぬ言い方のあと、「それもそうだよな~」の、ひと言でこの話が終わった。こんな梨本課長とのお付き合いはとても気が楽であった。
ある日の東京営本で
「当館の企画商品(チラシ)を、支店のパンフレットスタンドに置いてもらえますか?」と、ある日、ネヲンは梨本課長に聞いた。
「あゝ、いいぞ!」と、梨本課長は二つ返事であった。
「なんなら、俺のところへ送れば、各支店に小分けして配送するぞ」と、言った。大会社の社員は、懐に入った者には鷹揚である。
「大企業(JTB)は、ウチみたいな零細企業(旅館)なんて、相手にしない」と、弱気な考え方は誤りである。だが、これは窮鳥懐に入ればという話ですから、まずは、しっかりとコミニュケーションを取る努力をしましょう。
磯料理(優)コース を携えて
ネヲン、早速、伊東市の印刷屋さんと独自の企画商品(以下、チラシ)の作成に取り掛かった。そしてすぐに「磯料理(優)コース」が完成した。新らしいセールス方法の始まりだ。伊東の印刷屋さんが、仲間意識をもって積極的に協力してくれた。

ネヲン、チラシを各支店へ直接配り歩く計画であっが、まずは、梨本課長の好意に甘えて、JTB東京営本から各支店への配送をお願いした。このシステムにのれば、JTBの真面目な社員達は、自社商品だと錯覚してくれると思ったからである。
この作戦は見事に的中した。ネヲンがチラシを持って各支店に出向くと、すべての社員がその存在を認識していた。さらに、驚いたのは「磯料理(優)コース」の取り扱い説明及び手配方法が、各支店のコンピューターに入力されていたのである。さすが梨本課長! 大会社は、凄いと思った。
さて、大企業の上意下達の凄さに驚いたネヲンであるが、これは、あくまでも周知徹底されたということで、売り上げが保証されたわけではない。
そこでネヲンは、販路の拡大を目指して、さらなる行動を起こした。

スタンプを押す
ネヲン、JTBのカウンターで、社員にでチラシの束を見せながら「スタンプを貸して」と頼むと、一瞬、彼ら彼女らは怪訝そうな顔をする。「お申し込みは」の空欄に、支店のスタンプを押すのは、カウンターの人たちの仕事だったし、かって、旅館の人がそんなことを言った経験をしたことがないからだ。
再度、スタンプを押すしぐさをしながらお願いすると、「私がやりますよ」と、言いながらもカウンターの下からそっとスタンプを取り出す。
すかさず笑顔でネヲンは、「いいよ、いいよ、手間をかけさせては申し訳けないから」と、いいながらポンポンとスタンプを捺す。こんな時はネヲン、社員を選ばない。それは、磯料理(優)コースを認知させるという魂胆があったからだ。
余談だが、このときスタンプ台が不要なシャチハタがあることを初めて知った。便利なものが出来たな~と感心した。
この話にはネヲンのもう一つの魂胆がにあった。
ネヲン、最後まで人の良さそうなフリをして、スタンプを捺し終わったチラシを両手でもって、パンフレットスタンドを目で指しながら、「隅っこの方に入れときますから」と、動き出す。社員の「そこまでしなくても」の声を聞きながしながら…。
誰がパンフレットスタンドの片隅になんかに置くものか、とネヲン。一番目立ちそうなところへ、そ~っと差し込む。ある時は、他のチラシを押しのけて…。
このチラシの成果は大きかった。世の中には、旅行業者が口銭(仲介手数料)を取ることが気に入らないとする人たちが一定数いるのだ。そんな人種の人たちが、チラシに書かれて電話番号を見て、旅館に直接、宿泊依頼をしてくる。なかには、150人もの団体さんがいた。
経験を積むとは恐ろしいものである。いろいろなずる賢い知恵が付くものである。さて、さて、更なる知恵をつけるためにまた歩き始めよう! 犬も歩けば棒にあたる。
< 完 >