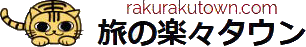職を探しに
この物語の主人公・オレこと「湯の街ネヲン」は、この時代のごく普通の体型でごく普通の男で、特に学業やスポーツに励んだことはない。ボーっとして生きていた。
1966年(昭和41年)春、大学は卒業したけれど、東京オリンピック後の昭和40年不況の真っただ中で就職口がなかった。当時、東京消防庁の荏原消防署長の親父が、管内の東証二部の昭和無線を紹介してくれたが、変な自尊心であっさりと断った。
そんなことから、国防なんていう大それた考えではなく、からだのオーバーホールぐらいの軽い気持ちで、日本初の大卒の二等兵として、陸上自衛隊にもぐりこんだ。
だが、平和な国の自衛隊員といえども「新兵さん」は想像以上に大変であった。自衛隊員としての基礎訓練の3ヶ月、続けて、業務遂行のための技術取得の3ヶ月、この新隊員教育時代は、ただただ寝ることが唯一の楽しみであった。
無線通信隊員として久里浜駐屯地に配属され、ト・ト・ト・ツーという通信業務にも慣れ、大型自動車免許取得のための操縦訓練では、初めて乗った軍用トラックの高い運転席からの三浦半島の美しさに感動した。しかし、試験にも無事パスすると毎日がとても退屈に感じるようになった。一に通信、二にラッパ、三に炊事のつまみ食いといわれる、楽な職種のせいもあったかもしれない。

ネヲンは、自衛隊の「有事に備える」というのは理解できたが、「有事に備える=同じことの繰り返し」という部分が性に合わなかった。どちらかというと、怠け者の部類に入るネヲンだが、ヒマ(暇)はイヤだった。与えられた仕事の中で、いかにサボろうかと知恵を巡らすのが好きなタイプだったからだ。
そんなワケでネヲンは、暖かく職住接近の職場をもとめて、ここ三浦半島と似た気候の伊豆半島へ出かけた。今となっては、その時の気持ちは思い出せないが、職探しには人口の多い伊東市のほうが有利なのに、なぜか下田市の職安を尋ねた。
伊東駅前で、レンタカーを借りて下田へ向かった。天気も良く道中は爽快であった。

下田の職安は歴史ある木造の建物で求人室は二階にあった。そこには、みるからに無愛想な風体の男性職員が一人暇そうにしていた。ネヲン、黙って求人票をくくった。求人票は、男は造船所の季節工だけで、女は旅館の女中さんばかりであった。
学歴の欄はすべてが中卒以上と書いてあった。ネヲンが、こりゃダメだとあきらめて帰ろうとしたら、彼の職員が、ぶっきらぼうに「兄さん、仕事を探しているのか?」と、声をかけてきた。後で思えば運命のひと声であった。
ネヲン、「かくかくしかじかで、会計事務所にでも勤めたい」と告げると、その職員は「会計事務所が、どこの馬の骨ともわからないヤツを採用するわけがないだろう」と、口悪くいいながら席を立ち、奥の部屋から一枚の求人票を持ってきた。
それは、熱川温泉「旅館 青雲閣」の求人票で、学歴欄には高卒以上と書かれた。そして、「今、紹介状を書くから、このまま面接に行け」と、無愛想な職員はなかば強制的に言った。ネヲン、ちょっとむっとしたが黙って指示に従うことにした。
旅館 青雲閣にて
職安で紹介された「旅館 青雲閣」は、温泉街の中心を流れる川を背に平坦になったメインストリート沿いにあった。三段ほどの緩やかな階段のさきに、唐破風の立派な玄関をもった木造二階建の旅館で、右隣りにはみやげ物店を併設していた。
少し後になって知ったことだが、「旅館 青雲閣」は、戦争中に東京から疎開した先代が1950年(昭和25年)に創業した。当時の熱川には旅館が6軒しかなく、客室は15室だったが3番目の規模を誇ったそうだ。
さて、温泉旅館のことなんて何にも知らないオレは、立派な旅館を見上げながら、こんな温泉場の、こんな旅館で、蒲団敷き、風呂掃除、庭木の手入れ、そして、休日には温泉三昧、海辺で読書…。と、そんな世捨て人のような人生もいいと思った。
が、この時のオレ、この旅館には海辺に建つ新館があることを知らなかった。
思い切って石段を登り玄関に入った。館内は真っ暗でシーンと静まり返っていた。ネヲン、紹介状を片手に「ごめん下さい」と、大きな声を暗闇にむけて投げた。少々の間をおいて、右手の奥から音もなくネヲンと同年配の色白の女性が出てきた。
ネヲンが来意を告げると、その女性は軽くうなずき声もなく暗闇の奥に戻っていった。ややあって、略図の書かれた小さな紙切れをもって現れ、行く先を指し示しながら、「このままココへ行ってください」と、ひとこと言って音もなく消えた。

略図に書かれた先には、伊豆大島が目の前に浮かぶ海岸沿いに、オープンしたばかりの青雲閣の新館「ホテル アタガワ」があった。小さな社長室に招き入れられたネヲンは、そこで、長い顔にぎょろっとした大きな目玉をもった社長の面談を受けた。
結果は至極簡単で、二本の長い指をネヲンの顔の前にたてて、給料は前職の2倍の15,000円を出すから都合がつき次第いつでも来いということであった。
しかし面談が終わったネヲン、気分がスッキリしなかった。それはネヲンが公務員の家庭に育ったからかもしれない。それと、小さい時から「お前はぶっきら棒だから、将来は事務員になれ、ソロバンも得意だし」と、言われ続けてきたせいもあった。

久里浜駐屯地に戻ったネヲン、ある夜、横須賀の繁華街、どぶ板通りの片隅で露店の占い師に手相を見てもらった。初めての経験であった。ネヲンが広げた手を見て、占い師のおばさんが、「あなたは、長男でもないのに長男の役割をしょって生きてきましたね」と、言った。
このときのネヲン、占い師の言葉にビックリした。ネヲンの生い立ちは、農家の三男として生まれたが、幼少の時に親戚の家に養子に出された。が、その養子先で2人の弟ができた。まさに、占い師の言った通りであったからだ。
さらに占い師は、温泉旅館で面接を受けたばかりにネヲンに、あなたは「水商売むきです」と言った。これが、ネヲンの生き方を180度かえる決定的なお告げとなった。
旅館生活のはじまり
1968年(昭和43年)の初秋、オレこと「湯の街ネヲン」は、ボストンバック一つをもって伊豆熱川温泉に生活の拠点を移した。いろいろな導きによって、自衛隊員から旅館 青雲閣、通称「ホテル アタガワ」の社員となった。
青雲閣の玄関先で、たまたま見かけた若い女性に「湯の街ネヲンです」と挨拶をすると、彼女は「あぁ…」と小さな声を上げ、早速、衣食住完備の「住」なるところへ案内してくれた。そこは、つい最近まで客室として使われていたと思われる広い部屋で、五つほどの万年床があった。
一番手前の2畳ほどのスペースに寝具がたたまれてあった。彼女はそれを指さし、ここで寝起きしてくださいと言った。ネヲン、自衛隊では頑丈なスチール製の2段ベットだったので、居住スペースが広がり、畳の上で寝られることがうれしかった。
そして初出勤の朝、仕事を教えてくれる「まち子さん」という先輩を、ホテル アタガワの雑然とした事務室の隅っこで待った。仕事は、宿泊料や飲料代などをいただく「お会計」係であった。とはいえ、会計係の机は貧弱な学習机のようであった。
そして先生は、なんと、あの時の女性であった。あの時は、日差しが強く館内は薄暗くてよく分からなかったが、ツンとした感じの色白美人であった。
オレ、内心でヤッター! であったが、そんな高揚感もすぐに吹っ飛んだ。仕事が一段落したあとで、「もう私、明後日から来ないから…」と、ぽつりとまち子先輩が言ったからである。
この当時は、温泉旅館に泊まったり、レストランで食事をすることが贅沢な行為とされ、温泉旅館等は都道府県の首長から料理飲食等消費税なるものを特別徴収せよと命じられていた。これって税金を扱うことなので、しち面倒臭い計算をして公給領収書(請求書)を作成しなければならなかった。
その公給領収書への記載はすべて手書きであった。さらに、すべての計算がソロバン一本だったのでかなり大変な作業であった。
悲惨
仕事が片付くとまち子先輩は、昼飯の場へと案内してくれた。電気のスイッチをいれると大きな調理台のうえで数多くのゴキブリが慌てて逃げ果せた。先輩は慣れているのかゴキブリを見ても騒がなかった。ここは、「食堂」ではなく厨房から独立していて、お客様用のご飯を炊く炊事場であり、酒類を保存する場でもあった。
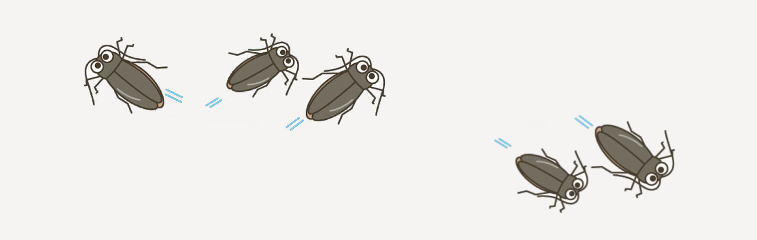
まち子先輩は、調理台に置かれた業務用保温ジャーを黙って指し示し、また、業務用のガス台の上の大鍋を指さし、「これに味噌汁があるから冷めていたら温めて食べな」と、言って口数少なく一人静に去って行ってしまった。
ジャーを開けたらイヤな臭いがした。くさいメシである。煮詰まった味噌汁を温めて、ご飯にかけてイヤな臭いをごまかしササッとかきこんだ。なぜか涙がこぼれた。
ホテル アタガワは三食まかない付きであったが、朝食と昼飯は、ほぼこのようであった。まともな食事は夕食のみであった。まともといっても、おかずはサバの味噌煮が一切れなどと一品のみであった。それぞれの名前が書かれた生卵が一個なんていう日もあった。
ホテル アタガワの社長が強欲で、従業員たちにこんな生活を強いていたわけではない。それが当たり前の時代だったのだ。当時の温泉街には、「鬼の暖流、地獄のいずみ、情け知らずの片波館」という旅館風刺の歌があった。温泉旅館はブラック企業だったのだ。
ただし、くさいメシが毎日だったわけではない。ご飯炊きのおばさんは、宴会後の200人~300人のご飯を用意するのだ。5升炊きのガス炊飯器で経験と勘を頼りに炊き上げるのだが、酔客が食べるご飯の量をピタリとあてるのは難しい。
ならば多めに炊いておけばいいと思うが、まだ、ご飯粒を残すと目が潰れるという思想が色濃く残っていた時代である。ご飯が無駄になるのを承知で余分に炊くなんて、ご飯炊きのおばさんのプライドが許さなかった。
心躍る
熱川の温泉街には信号がない。当然、スーパーもコンビニも、パン屋はもちろんなんでも屋もない。ネヲンが、こんな食生活に耐えられたのは、「早飯早ぐそ芸のうち」と、メシは腹を満たものと教育された前職の自衛隊のおかげである。
自衛隊の食事は、ボリュームもあり栄養満点だったが、調理をする隊員たちが三か月交代なので、ご飯は硬かったりべちゃべちゃだったり、おかずの味もイマイチであった。それに、いちどきに500~1000人分の食器を、隊員たちが巨大な洗浄機で処理するので、器はキズつき、うすぎたなく感じるので見た目もよろしくなかった。
さて、そんなネヲンの食生活にも楽しみがあった。それは、まだ青雲閣も旅館営業を続けていたので、ネヲンは、お会計の後始末などで、ホテル アタガワとの間を行き来をしていた、そんななかの青雲閣でうまれた。
青雲閣の調理場から、絵本にでてくる魔法使いのような顔のご飯炊きのおばあさんが、ネヲンをみつけると、いつも「さあ、食べな」といって、たくあんを二切れのせたホカホカのどんぶり飯をふるまってくれたのである。
青雲閣の調理場は昔のままで、ご飯は薪で炊いていた。宿泊者が少なかったのご飯の段取りは容易だったのであろう。若かったネヲンは、いついかなる時でも、出されたどんぶり飯はぺろりと平らげた。この時のどんぶり飯の美味さは、今でも自分史上第一位である。
こんなとき、いつも「ネヲンさん」といって近づいてくる調理補助の女の子がいた。「私、来年は18になるの! そしたら着物を着て女中さんになるんだよ」と、嬉しそうに、そして、自慢げに言った。
「湯」と相性がいい?

自衛隊はカレンダー通りの勤務で、8時から17時までで食事は栄養満点であった。一方、ホテル アタガワは、劣悪な食事と仕事といえばシーズン中は休みなし、朝起きてから寝るまでという最悪の職場であった。
旅館は普通の人間ならば耐えられないようなブラック企業であった。が、この時のネヲンは、堅苦しさを感じた自衛隊時代よりも、あんなこと、こんなことのすべてが未知で興味深い温泉旅館生活が、10倍も楽しく自由だと思っていた。
「水が合う」という言葉があるが、温泉旅館勤めをはじめたネヲンには「温泉が合った」のだろう。毎日が楽しくてしかたがなかった。もしかしたら、あの占い師がいったように、自分自身では気がつかなかった「水商売の適性」があったのだろう。
ちなみに水商売の適性者とは、芯の部分に「真面目さ」というものを持っていて、あとは分厚い「いい加減さ」を身にまとっている人間である。水商売の世界では真面目さが勝った人は行き詰ってしまうし、いい加減な人は、どぶ川の澱みのはてに流されてしまう。
熱川の名は「濁川」
熱川温泉という名の由来は、昔、この地に温かな川が流れていたからだという。今では湧出する温泉のほとんどが旅館などで有効利用されているが、かっては、自噴するままに川に流れ込んでいた。
伊豆熱川駅に降り立ち、目の前の噴泉塔(源泉櫓)や、眼下のあちこちからからモクモクく立ち上る湯けむりを見れば、川の流れが温かそうなのは、あなたも感じるでしょう。ちなみに自噴する源泉の温度は、ほぼ100度です。

ネヲンは、入社間もない穏やかな秋空のもと、昼の休憩で寮に帰る若い女中さんの「スヱちゃん」と一緒になった。スヱちゃんは、南伊豆町の農家の出で、色が白く笑うと目がなくなる可愛い娘だった。その昔、伊豆へ流刑になった公家さんの子孫のような雰囲気があった。そして、伊豆の自然のことなどをよく知っていていた。
大田道灌の碑を右にみて、赤い権現橋の上で、「ネヲンさん、この川の名前を知っている?」とスヱちゃんがいった。オレは穏やかな川面を見ながら「知ってるよ、熱川だろう」と、自信をもっていった。が、スヱちゃんの答えは「違うよ、濁川っていうんだよ」と、にわかには信じがたいものだった。
普段は穏やかな流であるが、大雨が降ると、この清流はあっという間に恐ろしいような激流となり海に注ぎ込み、たちまちのうちに河口を黄土色に変色させてしまう。
ネヲンが、ああ本当に濁川だと実感したのは、それからず~っとあとの大雨が降った日である。黄土色に変色し牙をむいたような激流を見て恐怖を感じたときであった。
時代は順風
1961年(昭和36年)伊豆急行線が開業し、1967年(昭和42年)には熱川区間に続き、稲取区間の工事も終わり東伊豆道路が開通した。これにより東伊豆の温泉地は東京からもアクセスしやすい観光地となった。
ここ熱川でも、海岸通りが拡張され、ビーチの南と北の端に大小の防波堤も完成し、ホテル旅館の大型化がはじまった。この頃には、時代の波にのって、ここの温泉旅館も発展し大小あわせて25軒にもなっていた。
この時のネヲンは、このあと温泉旅館業界が凄まじい成長をすることを知る由もかった。時代の波に乗るというは恐ろしいもので、スタート時のネヲンの年収180,000円が、15年後の退職時には、5,000,000円もの年収になっていた。
この当時の伊豆は新婚旅行ブームの真っ最中で、東海バスの社史によれば、1967年(昭和42年)の3月28日には、なんと、1,400組もの新婚さんが伊豆半島をめぐる定期観光バスに乗車したとある。ちなみに、車中での新婚さんたちのようすを聞かれたバスガイドさんたちは一様に答えた。皆さんよく寝ていましたと…。

旅館業界の人たちにはいい風が吹き始めていたが、世間の人たちの温泉旅館を見る目は厳しかった。ネヲン、仕事にも慣れ転職の旨を実家に告げに行ったら、両親は露骨に嫌な顔をした。かつ、「そんな仕事では世間体が悪いから、しばらくはこの家に近づかないでくれ」と言われた。
世間の人たちは温泉旅館を、食い詰めた流れ者たちの行き着く先と決めつけていた。そこは、風紀の乱れた場末の吹き溜まりでドロドロの愛憎劇の舞台とみたてていた。娯楽の少くなかったこの時代、そこで演じられ物語を興味津々と見聞きしていた。
しかし、二十歳そこそこのハツラツとした女中さんでいっぱいのホテル アタガワで働くネヲンには、そんな話が身近なものとは全く感じられなかった。
同じ頃ネヲンは、社長にも似たようなことを言われた。「ここ(温泉場)は、ウジ虫やゴキブリが這いずり回る場末のジメジメとしたごみ溜めだ。お前のようなインテリには住みにくい場所だぞ。出ていくなら今をおいて他にはない、よく考えろ」と、決断を迫った。
二等兵として自衛隊でもまれてきたネヲン、いまでは青白きインテリではなかった。「ここが気に入ってます。これからもよろしくお願いします」と、即答した。
それとネヲンは、生まれながらのとてもいい「気質」をもっていた。ネヲンにも人並みの喜怒哀楽はあったが、その場面、場面で感情がピークに達すると、無意識のうちにその感情をリセットして平常に戻れた。いわゆる、喉元過ぎれば熱さを忘れるタイプである。だからストレスがたまらない。
それ故に、大卒としての二等兵も務まったし、親や社長に何を言われてもどこ吹く風で、涙がこぼれたくさい飯でも腹に収まればすぐに忘れられた。素晴らしい!
まち子先輩の後日談
秋が深まった。ネヲンの旅館生活も、早や三ヵ月が過ぎようとしていた。この頃になって、お会計の仕事も大過なくこなせたし、館内の流れも把握できるようになった。
本館の青雲閣は、社員寮でもあったしみやげ物店も併設していたし、備品倉庫、洗濯場をも兼ねていた。当時の旅館には、「洗濯のおばさん」がいて、浴衣、シーツ、枕カバーなどのリネン用品は、自館で洗濯をしてそのおばさんたちが管理していた。
天日干しの浴衣やシーツは、バリッとしていて清潔感があり、お日様の匂いがして心地よかった。でも、天気の悪い日が続くと、おばさんたちの機嫌が悪くなった。

この地で初めて寒さを感じたある日の午後、熱川橋のたもの青雲閣みやげ物店でまち子先輩を見つけた。北向の店内には、海からのつめたい風が吹き込んでいた。「明後日から来ないから」の言葉に、すでに退職したものと思い込んでいたオレは、うれしくなって駆け込むように店内に入った。
七輪に手をかざし暖を取っていたまち子先輩に、「先輩、寒くないですか?」と、声をかけた。「平気だよ」といって、両足を七輪の端に乗せて「おまんたん火鉢をやっているから」といいながら、大きく口を開け白い歯を見せて「あはははは…」と笑った。まち子先輩の明るい一面を見たネヲンは、なぜかホッとした。
後日、まち子先輩が、静岡県を代表する下田市の名門女子高の出身だと知った。それを知ってネヲン、あの日の職安で、あの無愛想な職員の行いのナゾが解けたような気がした。そういえば、ここの社長は、東北の国立大学で農業び、東芝に勤めていたという異色の人であった。いち早く人材の重要性に気がついて、いろいろと手をまわしていたのだろう。
晩秋の熱川温泉
秋の新婚旅行シーズンが終わりに近づくと、熱川バナナワニ園に隣接する、東海バスの熱川営業所に着く定期観光バスから降りる新婚さんの姿がめっきりと少なくなる。
熱川バナナワニ園は、バナナがまだ高価だった1958年(昭和33年)に開園した。園内は温泉熱の利用により、バナナはもちろん熱帯性スイレンやオオオニバスなどの熱帯植物たちが季節を問わず咲き続けていてそれは見事です。
ワ二だけではなくレッサーパンダやゾウガメ、フラミンゴやマナティなどの珍しい動物たちも、まじかに見ることが出来ます。

いまでは熱川バナナワニ園で、とれたてのバナナが買えるという話があります。はたして、そのお値段は? バナナワニ園と一語ずつゆっくりと三回くり返してみて下さい。お値段がわかりますよ!
さて、年も押し詰まって、最後の最後にやって来るお客さんは、老人クラブや同窓会などの年配者たちだ。なんと、この人たちの予約は、宿泊可能日を問い合わせるハガキからはじまった。宿泊料金を安くしてもらうので、旅館の都合に合わせますという配慮からである。当時のおじいちゃんやおばあちゃんたちは礼節をわきまえていた。
さらに、安く泊めてもらったお礼にと、売店でたくさんのお土産を買ってくれた。そこには、泊ってやるという振舞いはまったくなかった。本当に、秋空のように清々しい時代であった。
にぎやかな大掃除
師走、世間では慌ただしさをます。ここ熱川の温泉街からお客さんの姿が消えると旅館もお正月を迎える準備一色となる。どの旅館の部屋の窓という窓に蒲団が干され、街じゅうが蒲団の満艦飾となり、午後になると窓際でパンパンとたたく布団の音が小気味よく響き渡っていた。
室内には、パタパタとはたきをかける音、シュッシュと箒で掃く音、雑巾がけのキュッキュッ…などという大掃除特有の音なき音がしていた。なんと当時は、板前さんたちも参加して、一部屋に5~6人もの若者が、群がって隅から隅まで磨きあげ、お正月のお客さんを迎える準備をしていた。本当の「おもてなしの心」があった。
ネヲンは、散乱しているものを整頓したり、汚れたものを磨き上げるのは好きだが、この大掃除というやつが嫌いであった。一つ一つの掃除の成果が見えないからだ。
そして、一日の作業を終えると、若い従業員達は思い思いに青雲閣の寮へと戻った。お客さんのいない時期は、ホテル アタガワでも世間並みに8時勤務であった。
寮といっても、個室があったわけではない。板前さんなどの若い連中は、広い部屋に集まって雑魚寝をしていた。ネヲンたちの部屋もそうであるが個人情報なんていう考えは全くない時代であった。早い話が布団のなかで寝られるだけで幸せであった。
それでも女中さんたちには、旅館創業時以来の女中部屋というがあり、そこには、それぞれに小物入れ用の引き出しがついた特製の二段ベットが壁沿いにずらっと並んでいた。女性たちの最小限のプライべートスペースが確保されていた。
ある時、ネヲンが部屋をのぞいたら、女中さんたちがベットから一斉に顔を出した。たくさんの亀が甲羅から首を出したように見えた。
温泉旅館は衣食住付きといっても、「食」「住」はこんなもので、「衣」は板前っさんに白衣、女中さんに着物が貸与されるだけで、フロント関係には何も出なかった。
露天風呂
青雲閣の大浴場には濁川を見下ろす大きな露天風呂が併設されていた。一段下がった川向こうの旅館の見事な赤松の庭園が借景で、とてもいい雰囲気があった。
時代はおおらかで、なんの囲いもない完全な露天風呂だった。下段からは、お客さんたちの話し声や下駄の音がストレートに響いてきた。でも、湯船のふちに登って立たねば、道行く人たちに裸体をさらすことはなかった。
男女それぞれの内湯とこの露天風呂はつながっていた。そう、露天風呂への出入り口には小さな突堤があり、そこには、おしゃれな竹垣の下部には花が植えられていた。男女が分けられているように見えたが、この露天風呂はほぼ混浴であった。
春と秋の旅行シーズンは、お客さんがいるので寮生たちは、夜遅くにそっと浴場を利用していた。しかし、シーズンも終わりお客さんがいなくなると、娯楽も少なく大型テレビも普及するずっと以前だったので、この露天風呂は、若者達が自然と集まり娯楽室みたいになった。
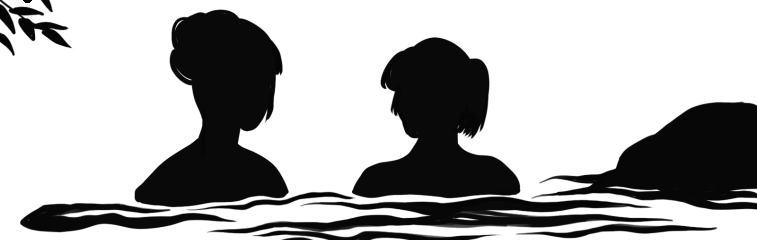
ある日のある夜、リーダー格の番頭さんが人差し指を口に押しあて「静かにしろ」との合図をおくりながら女風呂のほうに目配せをした。女風呂から笑い声が聞こえたのである。
リーダーは、男女を分ける突堤に取り付き、ガマガエルのような格好で竹垣の下の隙間から女風呂を覗いた。他の若者も静かに湯をかき分けながら突堤に取り付いた。男たちのガマガエルのようなうしろ姿は見づらかった。
ネヲンはこの劇場に参加しなかった。品行方正だったからではなく、近眼だから覗いても見えなかったからだ。メガネがとても高価な時代であり、風呂場では湯気で曇って用をなさないので、風呂場ではいつも裸眼であった。

「コラー!」
若い男達にとってのこの興奮の劇場も、突然、幕が降りる。露天風呂に面した二階の廊下の窓が勢いよく開けられ「コラー、お前等なにしてる」と、元気な女中さんの一喝で、ザ・エンドであった。男たちバシャバシャと湯をかき分けながら競ってその場を離れた。
参考であるが、覗かれた娘たちの反応には二種類あった。「キャ~」との悲鳴とともにすぐ逃げる娘と、「バカ、このスケベ」と反撃する娘である。男性天国の時代であった。これが今の時代であれば死刑に値するだろう。
たくあん漬け
年末のもう一つの行事は、大掃除の合間を縫って行われる「たくあん漬け」である。舞台は、海沿いの温泉街から急な坂道をのぼった先にある奈良本という古い集落で、ミカン畑を通り抜け、濁川の源流部にある小さな田んぼの脇を流れる小川である。
そこには、通称、おばあちゃん(社長の母親)の熱川隠居所であり、旅館で使用する一年分のたくあんの貯蔵所でもあった。

早朝、板場の若い衆が運転する2トン トラックに板長が同乗し、漬物業が盛んな埼玉県岡部町へ干し大根を仕入れに行き、夕方には、荷台をいっぱいにして帰って来る。
たくあん漬けは、板長が干し大根を仕入れに出かける一週間ほど前に、隠居所のすぐ隣を流れる濁川の畔に、板場の若い衆が大きな空の桶樽を並べることから始まる。
当日の朝、思い思いの身なりで集まった従業員たちに、青雲閣の創業時から勤めるという口数の少ない大番頭さんが、荒縄で自らが作ったタワシを配った。この大番頭さんはとても器用で、このあと大きな門松を作り旅館の玄関前に飾った。
荒縄のタワシを手にした者たちは、思い思いに小川のふちで桶樽にこびりついた糠をごしごしと洗い落とした。初めてのたくあん漬けをするネヲン、まだ寒さしらずだったので「春の小川はさらさらいくよ」と、口ずさみながら楽しく作業に励んだ。
天地返しをされ赤茶けた田んぼと土手の草はみんな枯れていたが、陽だまりでは気の早いセイヨウタンポポが小さな黄色い花をつけていた。秋が遅くきて春が早い、観光地ではない、伊豆の田舎の風景がそこにあった。
たくあんを使い切って空になった桶樽を、しばらく放置しておくと木が乾燥して収縮し隙間ができたりタガもゆるむ。それを元に戻すために水を張ってしばらく放置する。そして後日、板長の指揮のもと、わいわいがやがやとたくあん漬けに励んだ。
余談であるが、青雲閣の魔法使いのお婆さんの特技は「たくあんの油炒め」で、それは、古くなった大量の「たくあん」を菜切り包丁で薄く切り、塩抜きをし、大鍋で油炒めをして甘辛く味付けをしたもである。オレ、「たくあん」に、たくあん以外の食べ方があったなんてはじめて知った。
もうすぐお正月

熱川の海岸沿いの切り立った崖のたもとの陽だまりに、ツワブキの黄色い花が咲くと間もなくお正月がやってくる。伊豆大島がくっきりと見え、月明かりとイカ釣り船の漁火が幻想的な季節となる。ツワブキのつややかな葉に黄金色の花は、伊豆の海辺によく似合った。ツワブキはここ東伊豆町の町花である。
年が押し詰まってくると、館内は静かであったが調理場だけは活気づく。板前さんたちが、お正月のお客さんを迎えるために、手間ひまかけてすべてのおせち料理を手造りしているのだ。その作業は大晦日の晩まで続いた。
ネヲン、戦後の貧しい時代に育ったので、食事とは、すきっ腹を解消するためのものだと思っていた。が、旅館勤めをして、板前さんが作る本物の料理をみたときは、その華やかな美しさに眼が丸くなった。自分がもっていた食事の概念が、きれいに吹っ飛んだ。
そして、いつか自分もお客さんになってこんな料理を食べてみたいと思った。既製品や冷凍食品がない時代の、手作りの料理を提供していた旅館の話しである。
しかし、旅館の料理に憧れたネヲンも、おせち料理にはたいして興味がわかなかった。それは、台所中をいっぱいにして母親が作ってくれたおせち料理と大差ないように思えたからだ。おせち料理に対する愛情は母親の方が勝っていると思ったからだ。
旦那さんの新年の挨拶

元日の朝6時、羽織袴姿の旦那さん(社長)を前に、総勢60余名の従業員が広間に集まった。はじめて参加するネヲン、聞くところによると、旦那さんの新年の挨拶があるそうだ。新しい年を迎えるために、新調された着物を着た若い女中さんたちと、パリッとした真新しい白衣姿の板前さんたちの姿がまぶしかった。
旦那さんの新年の挨拶は、世の中が平穏であることと全従業員が心身ともに健やかで穏やかな正月が迎えられたことの喜びを、ニコヤカにそして簡単にのべた。
挨拶が済むと、板前さん女中さんと朝の仕事が忙しい順で、大番頭さんが注ぐお屠蘇の前へと集まった。余談だが、酒飲みはこんなときでも一番大きな杯を取る。
お屠蘇をいただいたあとは、旦那さんの前で一人ずつ「おめでとうございます」と新年の挨拶をする。旦那さんは、下位職の人ほどおおきな笑みを返しながら「おお…」と言葉にならない言葉を発しポチ袋をそれぞれに手渡した。素晴らしい日本の正月の風景であった。
ネヲンのポチ袋には、月給が15,000円だというのに、三つ折りにされた新品の1,000円札が3枚も入っていた。

元気な女中さん
新年の恒例行事がすむと、女中さんたちはポチ袋を、着物の襟元に差し込みながら足早にそれぞれの持ち場へとかけていった。そして、初日の出を拝むお客さんたちにあわせて、縁起のいい桜茶が用意された茶器セットを持ち客室のドアをたたいた。
女中さんたちはよく動きまわった。若さだけが理由ではない。当時の旅館の従業員たちには、上流階級とか、労働階級といった階級制度の意識があったわけではないが、お客さんたちは雲の上の存在であり、自分たちとは違う世界の人たちだから、奉仕するのが当たり前だと心の奥底から思って動き回っていた。
女中さんたちは、お客さんたちの気持ちを汲み取って、しごく当たり前のように先へ先へと動いた。当然、どのお客さんたちも女中さんの働きに見合うだけのチップをくれた。特に三が日は想像を絶する金額となった。
ある日ネヲンは、確認事項があってお客さんの部屋を尋ねた。ドアーが半開きなっていたので覗き込むと女中さんの履物が見えた。ふすまの向こうから、たどたどしい標準語で受け答えする声が聞こえた。えっ!、これがいつも伊豆弁でまくし立ているあの娘の会話かと思ったら、声にならない笑いがわいた。
ネヲンは、ずっと後になって考えた。旅行中に感じる、しみじみとした感情や旅情、すなわち「旅心」って、都会人と田舎人が触れ合って生まれるものだと思った。この時代には、旅心が生まれる素地があった。だが、時が過ぎ日本人が一億総都会人化してしまった現在は、旅心がなくなってしまったようだ。
庶民が温泉旅館に泊まるときは、テレビや週刊誌などで知った知識をふりまわし、殿様気分で偉そうにするべきではない。奮発して予算の三倍ぐらいの旅館を選ぶべきである。そうすれば、そこには庶民の知らない世界がある。知らない世界のことには文句のつけようがない。未知の見分は、世間も広くするし心も豊かになる。

ホテルの正面の海上には伊豆大島が横たわっている。6時54分、初日の出がその伊豆大島の右端から顔を出した。お客さんたちから歓声と拍手がおこった。当時の熱川の海岸線は、護岸工事の前だったので太古の人たちが見たと同じ朝日だった。
海岸線といえば…。
オレがホテルの前の防波堤で海を見ながらお客さんの到着を待っていると、いつも「何を見ているの?」といいながら、由美ちゃんという若い女中さんが横に立つ。由美ちゃんは、南伊豆町の出身でネヲンの横に並ぶとすぐに腕を絡め腰骨に圧を感じるほど体を寄せてくる。まるで子犬のようにかわいかった。
由美ちゃんは、「ネヲンさん、伊豆七島がどのように並んでいるか知ってる?」と、いって「音に聞こえし神津島、三宅、御蔵は八丈に近し 」と、おばあさんから習ったという言い伝えを歌うようにいった。
伊豆七島は正面の大島から右へ、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島と並び、右へ行くほど八丈島に近い。「 音に聞こえし… 」のなかには、大島、利島、新島、式根島の四島の頭文字が読み込まれている。今では式根島を七島には数えないで、八丈島を含めて伊豆七島というのが一般的なようだ。
さて、伊豆大島の三原山から上空高く噴煙がたなびく日がある。それは、ハワイのキラウェア火山やイタリアのストロンボリー火山と共に、三原山が世界三大流動性火山だからだ。また、三原山は火口上空の雲や噴煙が火口の赤熱溶岩に映えて明るく赤く見えることがある。この火映(かえい)という現象を、地元の人たちは昔から「御神火様」といってあがめていた。

由美ちゃんには特技があった。午後三時になると女中さんたちは、お客様をお迎えするためにおそろいの着物姿でロビーに集まってくる。
ネヲンがお客様の到着を待つ間、堤防にボールをぶつけて遊んでいると、由美ちゃんが、「私も」と言いながらグローブをもって出てきた。初めての時はびっくりした。着物姿とキャッチボールが結びつかなかったからだ。
ネヲン、おそるおそる山なりのスローボールを投げた。すると、外せば海ポチャだというのに、びっくり仰天、かなりのスピードボールが胸元に返ってきた。聞くところによると、ソフトボールのクラブ活動でキャッチャーをやっていたという。
冬休み
晴れやだった三が日もあっという間に過ぎた。松の内が明けると、旦那さんは、また全従業員を集めて休業宣言にちかい訓示をした。
「やがてくる春の旅行シーズンに備え、風邪など引かないように体の手入れをしっかりして、充分に英気を養っておくように」といって、3月までのほぼ二ヶ月間も遊ばせてくれた。もちろん給料は全額支給である。
当時の温泉旅館にはものすごい財力があったのだ。現在では考えられない時代である。この余裕から本物のサービスが生まれたのだ。
冬休みになると、伊豆出身の女中さんたちはめいめいに実家に帰った。館内が寂しくなったが、オレは勘当も同然だったので帰る家もなかった。また、遊びに行く金もなかった。故郷のおみやげを持って帰ってくる娘たちとの再会を楽しみに静かに日々を送った。
そして、夜が更けるとオレは一人もくもくと、ひと気のない内場の片隅でわずかばかりの洗濯をした。小さなタイルの目地を洗濯板代わりにシャツとパンツと靴下を洗った。暇になると億劫だった洗濯も楽しみの一つとなった。
熱川温泉ではじめての冬をむかえたオレは、毎日がワイシャツ一枚で過ごせた。ここでは冬支度が不要で、文字通り常春の伊豆だと思った。が、次の年の冬は今まで通り寒さにふるえた。人間の環境適応力の素晴らしさを知ったネヲンであった。
春の旅行シーズン
熱川の海岸通りは天城連山の山ひだが切り立つように海に落ち込んでいる。そこの住人たちは、吹き抜ける風や降りそそぐ陽光、潮の匂いや海の色、伊豆七島の島影などから季節の移ろいを感じとった。春先になると相模灘から東風が吹く。

1969年(昭和44年)3月、温泉旅館のことが少しわかってきたネヲンに、ここ熱川温泉でむかえる春の旅行シーズンが始まろうとしていた。
4月、5月、春たけなわ。新婚さんに混じって、慰安を目的とした社員旅行の団体さんも次々にやってきて、文字通り連日が満館となった。シーズン真っ盛りの温泉街は、お客さんであふれかえっていた。はじめてのトップシーズン、ネヲンは、眠らない温泉場に異様なものを感じた。
温泉旅館の連日満員というのがどれだけ凄いかというと、お会計係りのオレ、というより男たちは、3月下旬から6月の上旬まで一日の休みもなかった。仕事好きのオレは、そんなことはちっとも苦にならず日々楽しく働いた。それに休日出勤手当の多さも嬉しかった。男は黙って働くのが当たり前の時代であった。
でも、館内を上へ下へと動きまわる女中さんたちは、人手もあったし、きっちりと休みが取れた。温泉旅館の主力である若い女性たちにはそれなりの配慮があった。
ネヲン、深夜に戻った青雲閣の露天風呂から眼下に見下ろす熱川橋は、浴衣がけの酔客が、橋からあふれてこぼれ落ちそうだった。ポン引きのお兄さんも人の多さで仕事にならないようであった。
うわさ話によると、ある旅館の夜警さんは日の出前の薄暗いうちに温泉街をぐるっと一回りしたそうだ。すると、サイフが二つ三つ拾えたからだ。拾った財布のそのあと行方ついては聞いてない!
悲鳴・・・
頭の痛い日もあった。ネヲン、宿直の当日の朝は真っ先に宿泊表を見た。□□土建、□□組、□□建設、□□工務店などの団体名が並んでいると、ああ、今夜は寝られないな~と憂鬱になった。
夜中、ロビーから怒声が響く。ロビーはだらしなく浴衣を着た酔客であふれかえっている。お客さん同士のケンカが始まったのだ。無秩序に集まった人たちが大声をあげながら渦となっている。浅草の三社祭をまじかで見てるようである。こんな時は手のつけようがなく収まるのを待つしかない。
時には目を据えて、「調理場から包丁をもってこい」などと言いながら事務室に入ってくる恐ろしい者もいた。が、それぞれの団体の幹事さんたちの努力もあって、小一時間もするとロビーは静けさを取り戻す。
時には鼻血を出して浴衣を赤く染めた人もいたが、ほぼ泥酔した者同士なので、お互いに手数は出しているがなかなか相手に当たらない。たまにヒットしても、その威力は平手打ちはどしかなかったので大事には至らなかった。
乱闘騒ぎの原因は宴会場にあった。例えば50人の団体さんなら、お銚子が250本、ビールが150本も出たからだ。凄まじい飲みっぷりであった。
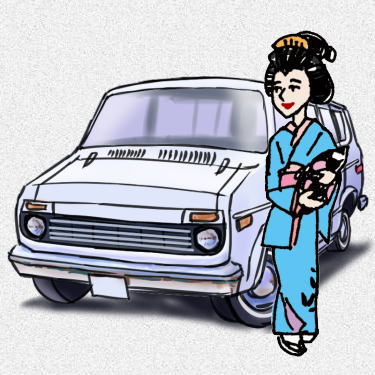
まだまだ庶民の懐も貧しく、健康問題なんて考えなかった時代である。社長は社員たちにたらふく酒を飲ませることを、社員たちはここぞとばかりに浴びるほど飲むことが、春と秋の慰安旅行の最大の目的であり、喜びでもあり楽しみでもあった。
宴会時に客席から「お~い、酒がないぞ」なんて声が発せられ、それが社長や幹事さんの耳に入ると、翌朝、支配人は「あれほど、酒を切らすなと言っただろう」と、こっぴどく吊し上げられた。そして、たくさん飲んだお客さんほど上機嫌で帰っていった。
裏側・・・
中国のことわざに、「上に政策あり、下に対策あり」と、いうのがある。宴会中に「酒を切らしやがって、気の利かねえ女中だ!」と、理不尽な叱責を受けた女中さんたちは、自己防衛のための対策を考えた。
これまでの、注文を受けてから酒類を提供するという習わをやめ、「幹事さん、お酒が切れそうです」と言って、幹事さんが「もういいよ」というまで、なかば強引に酒類を提供し続けた。おかげで、女中さんたちはマイペースで仕事が進められたし、怒られず、なおかつ売り上げが大幅にアップした。社長さんは儲かって一人喜んだ。
さて、徳利は、先がとがっている「注ぎ口」から注いではいけない。とか、徳利の中身がなくなったら、寝かせておくのが作法など言われているが、間違いではないが正式なルールでもマナーでもないそうだ。
そして、お酒が売れれば、それを手配する用度係は大忙しである。団体客が3~4組も泊まれば、宴会のスタート時にはお銚子を150本も200本も用意しなければならない。そしてすぐに、100本も150本もの追加が来る。こんな時は、酒燗器なんて何の役にも立たない。そんなのに頼っていたら夜が明けてしまうし、怒鳴り飛ばされる。
大鍋に5升もの日本酒を注ぎ入れ、それを煮たて、柄杓ですくって大きなヤカンに移し、並べてある大量の徳利に流し込むのである。いやはや、大変な舞台裏であった。
芸者置屋のおとうさん
ネヲン、去年の秋の旅行シーズンは無我夢中で自分の仕事しか見えなかったが、この春のシーズンには、いろいろなことが見えたし気になることもあった。その一つが、夕暮れになるとアメ車にのってやってくる「おとうさん」と呼ばれる人である。

アメ車が横付けした
日が暮れて、宴会がはじまる6時近くなると、いつも、玄関さきに外車が横付けした。三味線を持った地方(じかた)の気難しそうなおばあさんと、若い立方(たちかた)の芸者さんたちが、なまめかしい香りを漂わせ、玄関先で元気よく「おはようございます!」といいながら降りてくる。
湯の街ネヲンは、いつも、この光景に羨望のまなざしを向けた。この外車を運転してくる芸者置屋の「おとうさん」にである。
聞くところによると「おとうさん」の仕事は、この芸者さんたちの送迎だけであった。昼間は、同じ置屋の仲間や旅館の支配人や板長たちと麻雀三昧だそうだ。仕事始めの夕方はピリッとしているが、夜10時、11時に、お座敷がはねた芸者さんをむかえに来るときは、「ヨッ、ネオンちゃん」と千鳥足であった。
しかし、こんな夢のような時代は長く続かなかった。旅館業界が人手不足の時代になると、置屋のおとうさんも、芸者のなり手を求めて四苦八苦するようになった。
そしてあるとき、ネヲンは腰を抜かすようなことにでくわした。いつものように「おはようございます!」と言いながら入ってきた芸者さんのなかに、見たような顔を見つけた時のことだ。なんとその芸者さんは、昨夜まで、ここの洗い場で皿洗いをしていたおばさんだったのだ。
その後、彼女がただのパートのおばさんだったのか、それとも、若い時に水商売の世界にいた人かは不明であった。
熱川海岸のなぞ
伊豆七島を望む熱川温泉のすぐ目の前に広がる海岸に築かれた堤防は、その南の端(下田より)は、「熱川大堤防」と呼ばれ、北の端(伊東より)は、「熱川小堤防」と、呼ばれた。今では「熱川YOU湯ビーチ」と洒落た名で呼ばれ、夏のビーチは若者から家族連れまでが楽しめる海水浴場としてにぎわっている。
さて、ホテル アタガワの目の前には、北の端の熱川小堤防があった。ネヲンが就職した当時の海岸の、このあたりの景色は今とはだいぶ違っていた。
小堤防の北側は穴切りへと続く岩礁で、南側は子供の頭ぐらいの丸い石がゴロゴロとした、いわゆる「ゴロタ浜」になっていた。寄せる波が静かにきて、ざぶーんと砕けて引き返すときに、ゴロタ石を動かしてゴロゴロと騒々しいような音を立てていた。
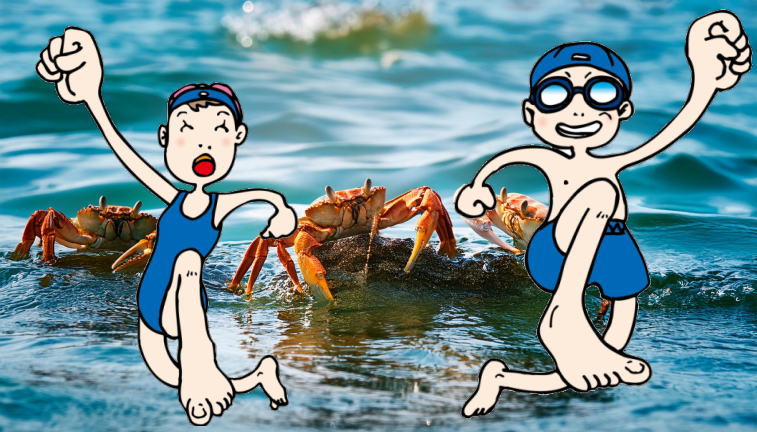
しかし、相模灘の風が爽やかに駆け抜ける夏が近づくと、大波小波が沖から大量の砂を運んできて、あっという間にきれいな砂浜へと変わった。その砂にのって透明で美しいシロギスもやってきた。が、このままきれいな砂浜であってほしいと思う人たちの願いもむなしく、秋風とともに砂は沖へと帰ってしまい、もとの石だらけの海岸に戻ってしまうという不思議な浜であった。
熱川温泉に夏がきた
7月も半ばを過ぎると、街じゅうに溢れ返っていた騒然たる音がすべて消えて、温泉街は、ひっそりと静まり返った。真っ昼間の温泉街には人っ子一人いない。が、活力と活気のおとなき音が街じゅうに渦巻いていた。
今の人たちには、旅館の三大繁忙期といえば、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始というが、当時の繁忙期は、春季の4・5・6月と、秋季の9・10・11月で、文字通り連日連夜、一日の休みなく満館が続いた。
そんな時代のホテル アタガワでは、「夏の暑さは体に障る」との旦那さんの一声で、旅館は夏休みとなった。いまでは、信じがたい時代であった。
夏休みになると、北海道から来ていた娘たちは、1か月もの長期帰郷をした。地元の娘たちは、また、1週間、10日と、実家に戻って旧盆を過ごした。ネヲンのように帰るさきのないヤツ等は、ギラギラと輝く太陽の下で磯遊びにふけった。
若いって素晴らしいもので、毎日、いくらでも遊び続けられた。この時ネヲンは、小堤防の岩礁で手のひら大のアワビを見つけ、板前さんにお造りにしてもらった。自衛隊時代に三浦三崎港でサザエのつぼ焼きを食べたが、美味さはその比ではなかった。
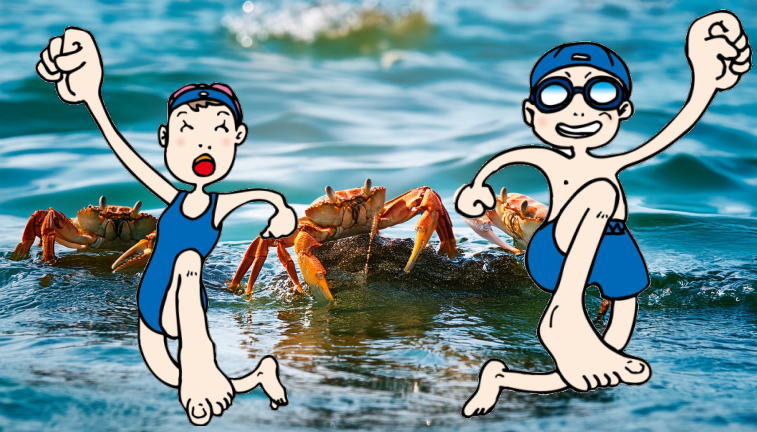
ただし、少しは仕事もした。遊びの帰りに海岸に流れ着いた流木を拾って帰ることだ。この時代は炊飯センターがなかったので、「ご飯」は、それぞれも旅館での自家炊であった。ホテル アタガワは業務用のガス釜であったが、魔法使いのお婆さんがくれた、青雲閣のどんぶり飯は、かまど炊きであった。その薪にするためである。
この時代、ホテル アタガワには20歳前後の女中さんなどの独身の娘が20人ほどいた。ある日社長が、「なかには言い寄ってくる娘がいるから気を付けるように」と、いった。が、ネヲンは男女関係のことに奥手だったのか、そんなことを意識したことがなかった。現に、後にネヲンの嫁になった女性はこの中にいなかった。
ホテルの売店係にシィーちゃんという、洒落たいでたちで目鼻立ちがはっきりした活発な娘がいた。ある日フロントの娘が、「シィーちゃんは止しな。あの娘は、洗濯が嫌いでパンツは脱ぎっぱなしだから」と、ネヲンに言った。
最後に、現在の温泉旅館業界では、8月13、14、15の三日間を、お盆特別料金期間と定めているが、当時は完全に休館であった。なにをつまらぬ昔話を…、というなかれ。昔と今、どちらがいい時代なんだろうか?
< 完 >