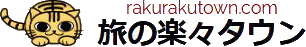はじめに
ページを開いて下さってありがとうございます。「旅の楽々タウン」の管理人・美馬 勝年です。そして、温泉旅館物語、初めての営業などでは、主人公の「湯の街ネヲン」として、また、東国へんろでは「ムラサキカイジ」で登場します。
幼少期
湯の街ネヲン(以下、ネヲン)が生まれ育ったのは、終戦直後の埼玉の北のはずれのなにもない農村だった。村の北側の視界のはてには、広く緩やかな裾野をもった赤城山が空と大地をわけていた。
寒い冬の日には、ビュービューと鳴く赤城おろしとともに、「強きをくじき、弱きを救う英雄」と称えられた、国定忠治が大勢の子分たちを引き連れて、山から下りてきそうなそんな気配が感じられた。
この村の一帯は、水の便が悪かったので、わずかな田んぼ以外はすべてが桑畑だった。コメがとれない農家は貧しかった。貧しくても子供たちは元気であった。
冬はケヤキの梢をピュウーピュウーと泣かせながら吹きおろす空っ風にさらされ、あかぎれとたたかい鼻水をすすりながら、乾いた畑の間をかけずりまわって遊んだ。
春が来た!
春がくると、村のようすは一変する。村じゅうが大人の背丈よりも高くなった桑の木につつまれ、視界は見上げた青空だけで、桑の葉のジャングルになった。

梅雨時になると赤黒く熟した桑の実にありつけた。夏にはさらに力強く成長した桑の葉を、ザワザワと騒がしくかき分けながら遊びほうけた。
が、桑の葉が生い茂る時期になると子供たちの遊びはしばしば中断された。人手を要するカイコの世話に親たちにかりだされたからだ。養蚕発祥の地の中国では桑の木は聖なる木という。夏季、村人たちはカイコと桑とともに生活をした。
運命のいたずら…。
ネヲンが小学校を卒業するころ運命のいたずらがあった。三男のネヲンは、東京の縁者のもとへの養子縁組が決まったのだ。生活環境が一変した。
当時の田舎の子は、高校へ進学する子はわずかで、中学を卒業すると農家を継ぐか、丁稚奉公に出るのが当たり前であった。が、ネヲンは大学にまで進学した。
このとき、ノー天気なネヲンは、漠然と、我が人生には目には見ないが素晴らしいレールが敷かれていて、この幸運はずっと続くものと思った。そんなわけで、せっかくの大学進学も、ダラダラとしたぐうたらな学生時代を送ってしまった。

ネヲンの無気力な生活とは逆に、世の中は上り調子で、畠山みどりが「恋は神代の昔から」を歌いあげ、都はるみの気合の入った「あんこ椿は恋の花」が、にぎやかでさわがしい商店街に大音量で流れていた。街は活気にあふれていた。
当然、大学を卒業したネヲンを採用してくれる会社は無かった。いわば、就活の落伍者となった。そんなネヲンが、ひきこもりにも、ニートにもならなかったのは、貧乏の厳しさを身体が知っていたからだ。
そして、親に庇護され生きてきて、最後に知ったことがある。それは、努力しないと結果は出ないということである!
大卒の二等兵!
社会人への入り口でストップをかけられてネヲンは、これからの人生を…、なんて、深刻には考えなかった。相変わらずノー天気なネヲンはつらつらと思った。そこで、社会の底辺で生きざるを得ない以上は、体力が必須だという結論を出した。

そしてネヲンは、衣食住完備で体力の増強が期待できるという単純な発想で陸上自衛隊にもぐりこんだ。入隊後に知ったことがある。四大卒の初めての二等兵だと…。
これが名誉なことなのか恥ずかしいことなのかは、ネヲンの思考の範疇外であった。勤務を終え、夜間高校へ通っていた先輩からは、おまえはいい性格だなと言われた。
同期の桜は、約50人からなる教育小隊が4個で、約200人であった。この頃から隊員の質が向上して3個の小隊は、ピカピカの新卒の高校生であった。それに対し、ネヲンが所属した小隊は、中卒、高校中退など、ネヲンのような者ばかりであった。
が、小隊ごとの対抗試合があると、いつも我が小隊が優勝した。人々の多様性の素晴らしさを、この時に知った。
ネヲン、いわば逃避先であったこの自衛隊員時代に、将来の糧となる宝物をたくさん手に入れた。ネヲンには、ここにも幸運のレールが敷かれていた。
まず一つ目の宝物は、
規則正しい生活のリズムと、隊員としての訓練を通して、なまった肉体が完全にオーバーホール出来たことである。健康な身体は、凡人の最大の武器である。
そして二つ目は、
新人教育訓練終了後、無線通信隊に配属されたことだ。ちなみに、自衛隊には、一に通信、二にラッパ、三に炊事のつまみ食いという、肉体的に楽な勤務の言い伝えがあるように、一般の歩兵隊員のような過酷な訓練を免れた。

が、ト ト ト ツーツーという、雨垂れのようなモールス信号と格闘する羽目となった。かって経験のない異次元の言語で遠距離と交信をした体験が、未知の世界への一歩となったし、複雑な通信機器類の操作もやればできるという自信となった。
ちなみに、ト ト ト ツーツーというのは、数字の「3」のことで、み つ き ゆー こー( 三月有効 )と、大きな声を出して身体に覚えこませた。
さらに、おまけがついた。
給料をもらいながら大型の自動車運転の教習を受け免許も取得した。危険物取扱主任者の資格もとれた。まさに自衛隊様々であった。
新世界へ…。
1968年( 昭和43年 )の初秋、自衛隊を3年で除隊すると、下田の職安の不愛想な職員にいわれるがままに伊豆熱川の温泉旅館に就職した。
ここで、またしてもネヲンは、その後の人生を決定づける幸運のレールにのせられていた。ここ旅館の社長が、ネヲンの能力をフルに引きだしてくれたのだ。悪く言えば、こき使われたのだが、生きる自信を獲得した15年間であった。
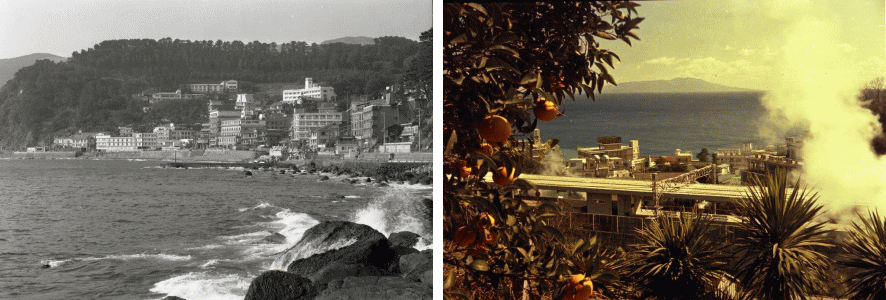
当時の伊豆熱川温泉は、戦後大ヒットした近江俊郎の湯の町エレジーのイメージどおり湯の香ただよう風情豊かな温泉場で、気候温暖、風光明媚、熱川バナナワニ園の異国ムードと相まって、新婚旅行のメッカにふさわしい観光地だった。
が、しばらくして、この静かな温泉場は一変した。高度成長の波が世間から少し遅れて、伊豆半島にも団体旅行という大波となっておしよせたのだ。
春と秋の観光シーズンには、夜になると温泉街の中心、熱川橋からは、ほろ酔いの観光客が、押し合いへし合いあって濁川へ転げ落ちそうであった。この人ごみに圧倒されポン引きのお兄さんたちも身動きが取れなかった。ここ熱川温泉は、にぎやかで怪しげな雰囲気をも併せ持った歓楽街的な温泉場になってしまった。
現在では観光業界といえばごく普通の産業であるが、その当時は世間から白い目で見られていた。そして、職場環境は今でいうところのブラック企業であった。
温泉旅館がブラック企業?
当時の旅館業の劣悪な労働条件を証明するかのように、地元の旅館従業員の間では「鬼の〇〇、地獄の〇〇〇、情け知らずの〇〇館」(〇〇には旅館名が入る)という哀歌があった。
さてさて「水が合う」とは理屈外のことである。
ネヲンは勤務の見本のような自衛隊生活よりも、なぜか、就寝時のフトンのなか以外は仕事場、休日はほぼ無しという旅館勤めに、精神的な開放感と肉体的な余裕を得ていた。これって説明のしようがない。
旅館勤めは、文字通り雲霞(うんか)のごとく押し寄せた大量のお客さんと、極端な人手不足とのはざまで翻弄され、もがき苦しんだ15年でもあった。が、働き甲斐もあった。例えば、初年度の年収の18万円が、15年後の退職時には、なんとなんと、500万円にもなっていた。
新・新世界へ…。
ネヲンは40歳で退職し起業した。確固たる計画と明確な目標があったわけではないが、このときもレールが敷かれていたようで、自動的に行く先を切り替えてくれた。

ネヲン、起業する。
あえて、転職の動機といえば、勤務先の旅館の社長父子のあいだに社長交代の時期がきたからだ。歴史小説を愛読していたネヲンには、旧主が引退するときは、自分も退くべきだと思っていたからだ。
そんな折に、仕事で知り合った友人が、業界用語で「総案」という全国ホテル旅館の総合案内所の開設をすすめてくれた。業種的は旅館業の延長線上にあったので、いとも簡単に飛び乗ったが、苦労がなかったわけではない。
サラリーマンと経営者が、まったく別の世界の生き物だということを理解するのに時間がかかった。植木等の「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」の本当の意味をこのとき知った。
総案の実務
総案とは、あふれかえる団体客で、旅館と旅行業者が目の前のお客さんの対処だけで精一杯という時代に生まれた新しい職種で、いわば、旅館と旅行業者を結び付ける便利屋です。お客さんの目には触れることのない観光業界の裏方の仕事である。
総案の具体的な仕事はアナログで、販売契約をした温泉旅館のパンフレットをもって、営業エリア内の旅行会社を片っ端から回り歩いて送客の依頼をすることです。
なんの商売でも同じであるが、旅館が総案に送客の依頼をしただけでは客はない。そこで旅館は、集客力アップのために現地スタッフを営業の応援として総案に派遣した。派遣といっても、旅館が暇になるウイークデーの2~3日間である。
総案が、この現地スタッフとセールス活動することを、業界用語で「同行営業」という。内緒の話しであるが、旅館の人たちにとっては完全な息抜きの場であり、総案にとっては昼食代やコーヒー代を負担してくるありがたいお客さんであった。
巨漢の営業マン
伊豆長岡温泉にわずか16室の料理自慢の小さな宿がある。ある日、そこの花山さん(以下、花ちゃん)という若い営業マンがネヲンの事務所にやってきた。

花ちゃん
花山さんという名前から、ネヲンは、かわいらしいお兄ちゃんを想像していた。が、ビックリな初対面であった。なんとお兄ちゃんは身長180cm超、体重は100kgをゆうに超えた堂々たる体躯の若者であった。
そして花ちゃんは、来所するとすぐに、60歳を過ぎ年齢的にパソコンは手に負えないと思っているネヲンを、体力にものをいわせて強引に説得し、ネヲンの事務所にパソコンを設置させた。が、結果的には、またしても幸運の女神がパソコンという宝物を運んできたのだ。
ネヲンが、パソコンは手に負えないと思い込んでいたワケは、前職の旅館勤務時代に、社長の大学生の息子が、ネヲンの会計知識をもとにベーシック言語を駆使し、秋葉原で部品を買い集めて、下田財務事務所のお墨付きの本格的な会計機を作くりあげた。大手のメーカーからは、プログラムの公開をしないようにとの懇願も受けた。
ネヲン、この時の経験でコンピューターとはすごくてすばらしいもの、というイメージが出来上がっていた。同時に、ベーシック言語のソースコードを見て、自分には、とても理解できるものではないと決めつけていたからだ。
さらにパソコンでは、もう一人感謝しなければならない先生がいる。優秀な友人が紹介してくれた「トーマス先生」です。またまた、女神が微笑んでくれた。この時、優秀な友人の友人は、みな優秀であるということを知った。
トーマス先生は、これまでホームページの作成には、ホームページビルダーという高価なソフトが必須だと思っていたネヲンの脳みそを完全に切り替えてくれました。なんと先生は、市販のソフトを使わず、いわば、紙とエンピツだけでホームページを作成する手法を伝授してくれました。このページがまさにそれです。感謝!